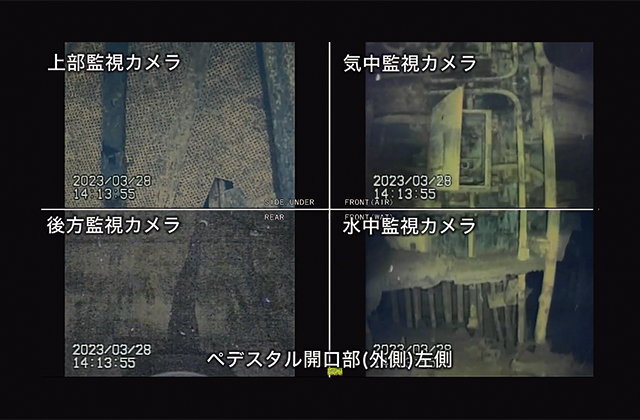【脱炭素時代の経済探訪 Vol.14】関口博之 /経済ジャーナリスト
ガソリンエンジン車は生き延びられるのか、それとも消え去る運命なのか。依然、見方は分かれているようだ。欧州連合(EU)はエネルギー相理事会で、2035年以降も、温暖化ガスの排出ゼロとみなす合成燃料を利用する場合に限ってエンジン車の新車販売を認めることに合意した。エンジン車全面禁止という当初案を修正した形だが、あくまで例外としての扱いだ。紙面には「エンジン車容認」「EUが方針転換」「日本メーカーは歓迎」などの見出しも見られたが、これで内燃機関が生き延びた、とまでは言えないだろう。35年以降の新車販売は原則ゼロエミッション車に、というEUの基本姿勢は変わっていない。
専門家からは、高価な合成燃料を使えるのは富裕層で、その顧客が選ぶポルシェやフェラーリが恩恵を受けるくらいでは、という冷めた声もある。“跳ね馬の咆哮”を愛すのは、一握りの人たちの優雅な楽しみになるかもしれない。

一方、日本メーカーから見れば、得意とするハイブリッド(HV)車やプラグインハイブリッド車の市場を、脱炭素化までの移行期において確保したいのが本音だ。その意味でガソリンエンジンの全面禁止を免れたことには安堵もあるだろう。ただ、今回EUの当初案に注文を付けたドイツにすれば、大事なのは国内メーカーの雇用であって、HV技術の温存といった思惑が働いたとは思えない。エンジン車にいわば逃げ道は与えられたが、EV化が加速するという大きな流れを見誤ってはいけない。
今回のEUの決定では合成燃料e―フュエルも重要なパーツになった。再生可能エネルギーで作る水素と、二酸化炭素(CO2)から合成される。燃やせばCO2が出るが作る時に回収したCO2を使っているため相殺され、排出ゼロとみなされる。ポルシェとシーメンスはチリで合成燃料の生産工場を稼働させた。日本でもENEOSなどが開発に取り組んでいる。
最大の課題はコストだ。経済産業省の研究会は国内の水素を使い国内で作る場合で1ℓ約700円、海外で比較的安価な水素で製造し持ってきても約300円と試算している。ガソリンの22倍弱から4倍にあたる。用途としても現状、電動化が難しい航空機用にまずはSAF(持続可能な航空燃料)としての供給が先になりそうだ。エネルギー業界もそう見ている。ただし車でも、新車はEVに置き換わっていくとしても、保有台数全体でみれば2040年代でも依然、エンジン車が多く走っている。実効性のあるCO2削減に合成燃料の役割は大きく、コスト低減が求められる。 それにしても130年余り前、ダイムラーとベンツがほぼ同時期にガソリンエンジン車を発明してから、内燃機関は素材、耐久性、燃費向上、軽量化など営々と先人の努力が注がれてきた。この磨き込まれた技術の粋が消えるのは何とも惜しい。水素エンジンは一つの道だが、技術史的にもっと何かに継承することはできないか。例えば機械式時計のように。専門家に尋ねたい気もする。
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.1】ロシア軍のウクライナ侵攻 呼び覚まされた「エネルギー安保」
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.2】首都圏・東北で電力ひっ迫 改めて注目される連系線増強
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.3】日本半導体の「復権」なるか 天野・名大教授の挑戦
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.4】海外からの大量調達に対応 海上輸送にも「水素の時代」
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.5】物価高対策の「本筋」 賃上げで人に投資へ
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.6】なじみのない「節ガス」 欠かせない国民へのPR
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.7】外せない原発の選択肢 新増設の「事業主体」は
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.8】豪LNG輸出規制は見送り 「脱炭素」でも関係強化を
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.9】電気・ガス料金への補助 値下げの実感は? 出口戦略は?
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.10】“循環型経済先進国” オランダに教えられること
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.11】高まる賃上げの気運 中小企業はどうするか
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.12】エネルギー危機で再考 省エネの「深掘り」
・【脱炭素時代の経済探訪 Vol.13】企業が得られる「ごほうび」 削減貢献量のコンセプト
せきぐち・ひろゆき 経済ジャーナリスト・元NHK解説副委員長。1979年一橋大学法学部卒、NHK入局。報道局経済部記者を経て、解説主幹などを歴任。