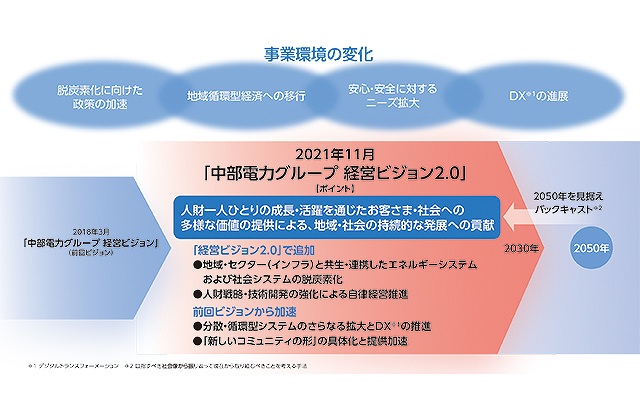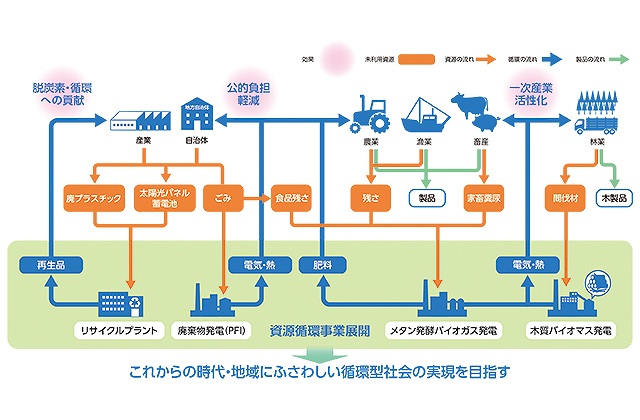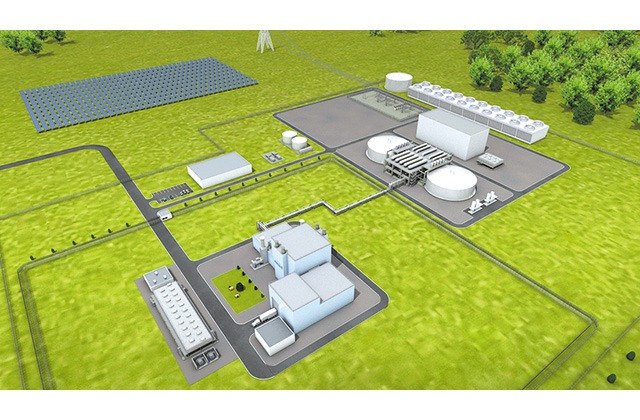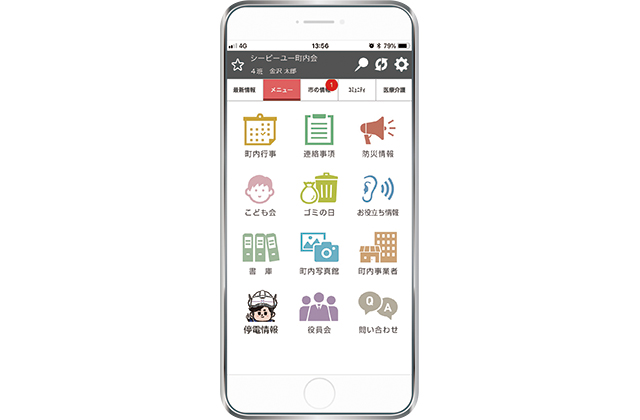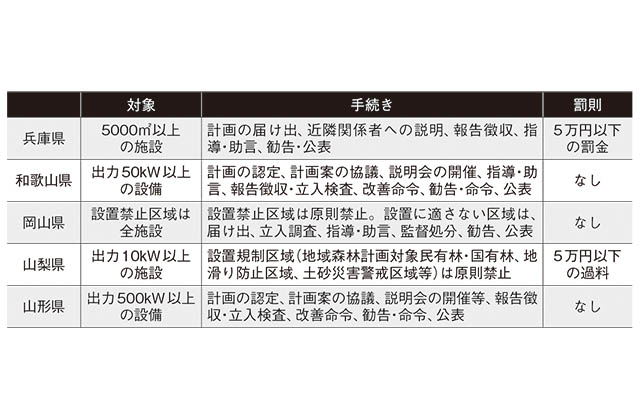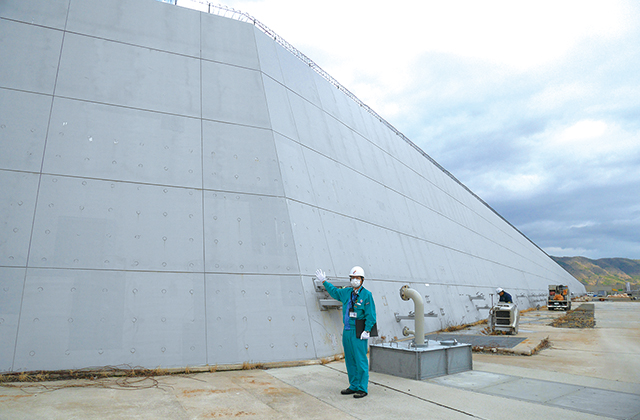飯倉 穣/エコノミスト
1,経済は、コロナ感染ショックで「収束なければ回復なし」である。コロナ前に比し5%程度の水準低下が続く。先行き米金融政策も気懸りである。その現実を直視せず、政策手段・効果曖昧なまま水準回復狙いも込め、22年度予算も高水準の歳出(支出)が続く。
「膨張 107兆円予算案 コロナ予備費5兆円 税収最高見込む 閣議決定」(朝日21年12月25日)、「107兆円予算案 減らせぬ費用多く 社会保障・国債費60兆円超 新規事業1%未満 成長に回らず」(日経同)。
報道も、コロナで諦めの体である。吟味・批判少なしである。そして財政見通しも暗い。
「高成長前提 遠い財政黒字、25年度目標維持、試算に甘さ「賢い支出」欠かせず」(日経22年1月15日)。只今、財政健全化展望なしである。いずれ国民の生活に塗炭の苦しみを招来しないか。今日の財政を考える。
2,22年度予算の経費内訳は、最大の社会保障費36兆円に次いで、国債費24兆円と歳出の23%を占める。一応公債償還原則60年と利払いを維持する。財源は、税収65兆円、借金37兆円(公債依存度34%)である。普通国債残高は、年度末予想1,026兆円で、GDP比184%である。繰言ながら当初予算ベース28年連続公債依存度20%超 (90年代前半10%台、後半20%台、99年以降30%台以上)、96年以降27年連続特例公債(赤字国債)発行となる。
この40年間、米国要求、オイル・円高・金融等ショックに加え直近はコロナ感染対策で、政治主導の「国を食い物に」する歳出を編成して来た。数字は物語る。巨額財政赤字への感覚麻痺である。我が国の長期にわたる公債依存度は、緊急対策、不況対策の位置づけを越える。なぜ消費税率を引き上げたのか、なぜそれまで財政頼りの経済とするのか。
3,この財政状況を憂慮する現職次官の嘆きも登場した。財務省作成「日本の財政関係資料」を見れば、破綻状況は一目瞭然である。他国との比較には、目を閉じたくなる。事務方トップのやや情緒的な論考は「バラマキ合戦の政策論に一言。国の長期債務残高はGDPの2.2倍、歳出と歳入推移が示す「ワニのくち」は拡大傾向、楽観的成長率を前提とした税収期待でよいのか。単年度財政収支をプライマリーバランス内に、社会保障制度持続に消費税は必要、引き下げは論外。財政破綻回避の努力が必要」と訴える(「財務次官、モノ申す「このままでは国家財政は破綻する」」文春21年11月号)。
これに対し次号で積極財政派の異見の紹介もあった。インフレ、財政危機に懐疑的な立場から、低金利・低インフレ・低成長なら財政出動は短期赤字だが、結果的に債務比率引き下げ実現と述べる。つまり財政出動が財政を健全化すると強弁する。L&Gの円天「使っても減らない通貨」を思い出す。
4,過去を振り返る。第一次オイルショック以降、経済低下に伴う財政出動とその後の財政悪化懸念・財政健全化努力の繰返しであった。財政再建の歴史も40年を超える。国民世論や経済の現状認識の読み違いによる失敗や後遺症が目立つ。例えば大平正芳内閣での一般消費税導入の失敗(79年)、中曽根康弘内閣の売上税導入失敗(87年)、細川護熙内閣の国民福祉税導入の失敗(94年)、橋本龍太郎内閣の六大改革に合わせた消費税増税実施と緊縮財政の組合せのタイミングの悪さ(97年)が目に沁みる。他方、不完全ながら前進例もある。竹下登内閣の消費税導入(89年)、村山富市内閣の97年4月実施の消費増税決定(94年)、野田佳彦内閣の財政再建・社会保障・税一体改革の関連法制定(12年8月)である。
5,財政赤字継続の論理は、様々である。まず経済論がある。不況時に財政拡大で需要創造・雇用確保というケインズ効果を狙う。最近登場のMMT(現代貨幣理論)派は、政府紙幣発行・財政支出拡大を是認する。
ビジネス、社会、政治サイドの強欲もある。低成長下、近時の経営感覚は、自立自営の精神を忘却し、苦境を国の助けで乗り切る姿勢が目立つ。国民のモラル崩壊もある。ほいど根性的社会保障の外延的拡大である。働く意欲の低下で、貧しさを国の責任・国頼りとする。朦朧状態のエコノミストの無責任さもある。また日本的思考(科学的精神不足)は、困難なことを回避・先送りし自分で決めない。
6,財政の基本は何か。経済の流れで財政を考えれば、生産、所得、支出で、支出の項目内にある。国民は、所得の一部を必要な公的サービスのために支出(税負担)する。その負担が国民生活の質を向上する。その際、財政支出のうち経常支出を税収で賄うことは、経済の原理、財政の基本原理である。公共投資を賄う建設国債の発行にも限度がある。公債発行に伴う金融市場の影響も無視できない。つまり国債は、金利を税収で賄ううちは、国民の財産で投資対象だが、金利を税収でなく国債で支払うことになれば、紙切れとなる。
各国の姿勢も様々だが、EUは、財政均衡目標(財政赤字GDP×3%以内、国債務残高GDP×60%以内)を掲げる。米国には「節約が第一の徳、公債は恐るべき最大の危険」(トマス・ジェファーソン1816年7月21日)の言葉がある。節度ある経済運営の必要性を示唆している。
7,政府の「中長期の経済財政に関する試算」(22年1月)は、財政破綻危惧もなく、何とか凌いでいけると繕う。現実は、低成長下で国家の借金はますます積み上がる。いずれ選択を迫られる。
第一の道は、縮小均衡後、安定経済の道である。国民負担(適切な増税と歳出の合理化)となる。第二の道は、財政破綻、スタグフレーションの道である。国民負担の先送りは、コストプッシュ等インフレ等の形で付けが回ってくる。第三の道は、財政を語らず、破綻待ちである。破綻後調整という投遣りである。第四の道は、拡大均衡型の経済成長期待路線の継続である。過去何度も挑戦し失敗している。根強い妄念が存在する。最近の民主党政権、安倍政権は名目3%実質2%を打ち出していた(机上の空論か数字合わせ)。いずれ第二の道に合流する。岸田政権はどの道であろうか。今後を見つめたい。
どのような対応を行うべきか。経済への影響を考慮すれば、まず歳入増を行い、その次に歳出削減することが賢明である。財政学は、政治学であることを改めて思い返したい。財政規律の言葉が示すように政治家の知性と理性と倫理観が肝要である。
【プロフィール】経済地域研究所代表。東北大卒。日本開発銀行を経て、日本開発銀行設備投資研究所長、新都市熱供給兼新宿熱供給代表取締役社長、教育環境研究所代表取締役社長などを歴任。