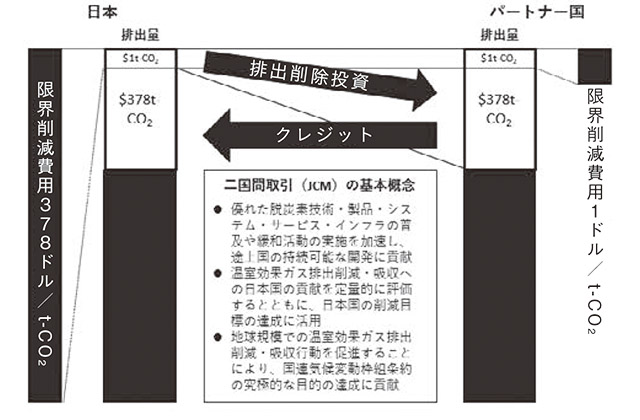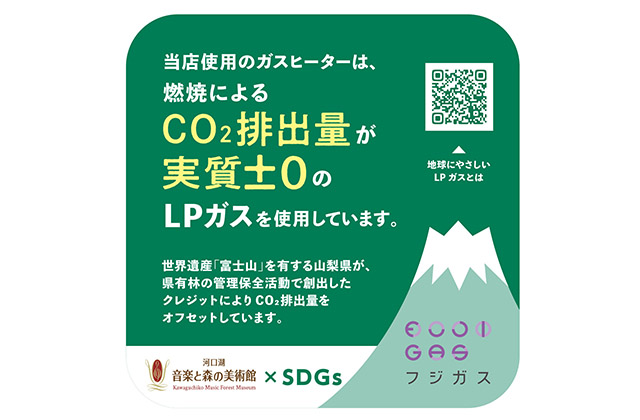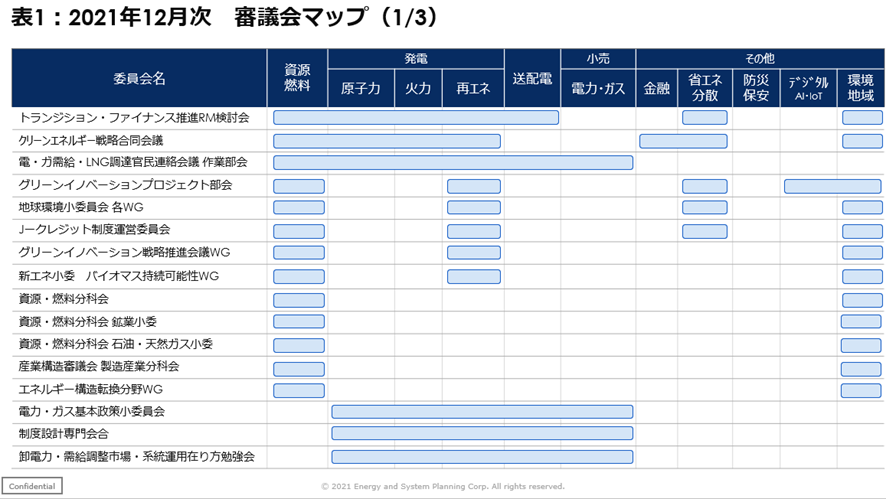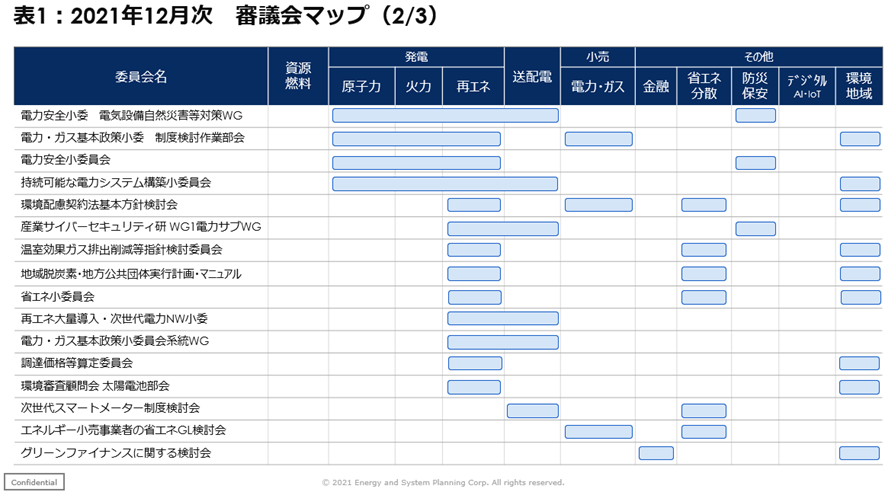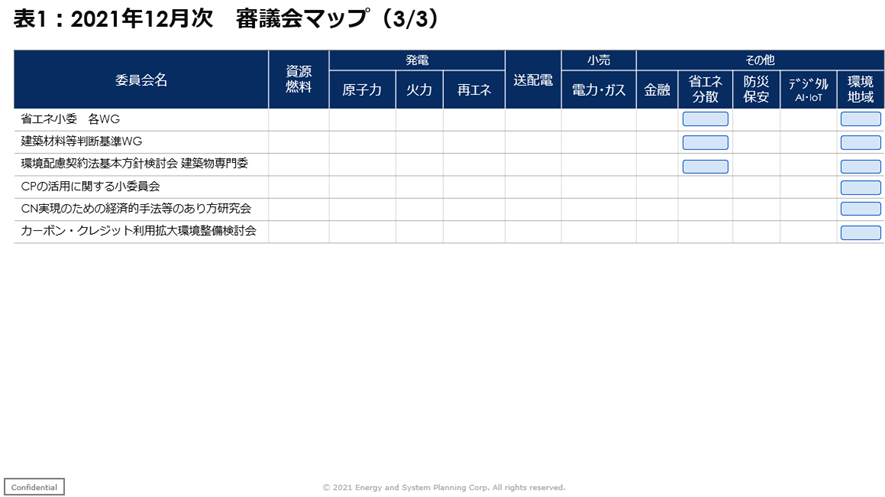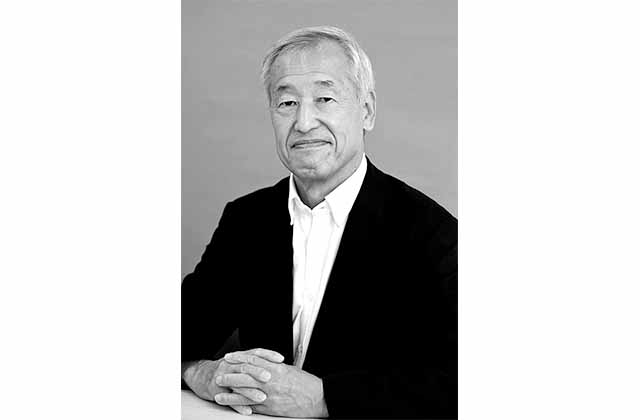【寿都町・神恵内村の文献調査】
高レベル放射性廃棄物処分場選定の文献調査が行われている北海道寿都町と神恵内村。 マスコミは「住民の分断」を強調するが、澤田哲生氏が現地で受けた報道とは違う印象を報告する。
澤田哲生(東京工業大学助教)
2021年11月中旬、私は6人の大学生のスタディーツアーに同行し、神恵内村に入った。ちょうどその夜、NHK北海道スペシャルが放映されていた。番組タイトルは『核のごみ~埋まらない溝~』。その番組の最後のナレーションが奮っている。
全国には少なくない自治体がこの問題に手を上げようとしていることを私は知っている。どこの自治体も、今次の事態を受けて政府・役所・事業者がどう出ていくのかをじっくりと注視している。
今こそ政治の決断と実行力が求められているのではないか。そうすれば、この処分地問題は前に進む―その実感を寿都と神恵内の地を踏んで、ひしひしと感じた。
「選挙が終わって、分断が残った」
しかしその後、つぶさに見た神恵内村には分断の「ぶ」の字もない。そして、寿都町では慎重派が〝文献調査の中止〟を直前に実施された町長選の争点に無理やり押し出してきたが、それも成らず町は平穏を取り戻していた。選挙が終わって残ったのは、実は反対派の内部分裂であった。
新聞、テレビなどメディアにとっては実に意にそぐわない状況がそこにはあった。
神恵内の爽やかな朝 数多くの観光スポット
神恵内村の朝を伝統の宿「きのえ荘」で迎えた。夜明け前に目覚めた私は眼下に広がる前浜を見下ろした。ひとりサーファーが波間に浮かんでいた。そして、空には満月が黄金色に煌めいていた。なんとも神々しく爽やかな朝である。ここの女将はいつも朗らかでお話し上手。いつでも泊まりたい居心地のいい宿である。
観光スポットに恵まれた神恵内村
宿を後にし、私たちはバスに乗って村内の観光スポットを経巡った。神恵内村はニセコ積丹小樽海岸国定公園内にある。美しい海岸沿いには奇岩が次々と現れ、その麓に袋澗がある。袋澗とは、漁獲したニシンを一時的に保管する大型の生簀である。明治から昭和にかけてニシン漁が沸騰した頃の名残である。あちこちに点在するので袋澗巡りのツアーもあるとか。
その後、村の新庁舎を訪ねた。髙橋昌幸村長自らが案内してくれた。庁舎を入るとすぐ目につくのは誰でも利用できる憩いのスペース。そしてその奥には幼児専用の可愛らしいトイレがある。これは村民を心から愛する村長の肝いりのトイレである。
新庁舎には津波を始め災害対策が十分に盛り込まれている。この庁舎は泊原子力発電所から30㎞圏内にある。庁舎の屋上付近には、非常用電源と庁舎内の空気を浄化するベントシステムが備えられていた。
いま神恵内村では新たな挑戦が始まっている。ニシンは去ったが、神恵内村はウニの名産地。ウニ漁は夏場が最盛期である。ところが、最近は陸の生簀でウニの養殖に取り組んでいる。餌は昆布ではなくなんとキャベツなどの野菜。温度調整をして、冬でも殻内に卵が入るように管理し出荷する。これをもって〝冬ウニ〟と称す。今後の期待の星である。
神恵内村を後にし、美しい海岸沿いに約1時間。寿都町を一躍有名にした日本初の町営風力発電所が見えてくる。
その脇に明治12年(1879年)建造の鰊御殿の威風堂々たる姿がある。御殿にはくぎを一本も使っていないという。実に見事な仏壇を始め、さまざまな細工に金箔がふんだんに貼られている。見飽きることのない建築遺産がここにある。この御殿を構えたのは越前から移住してきた民で鰊景気を先導したのである。かつて北前船でこの地域と越前は、物流と人流で結ばれていた。
寿都町が最近力を注いでいるのはバジルの水耕栽培である。近くのハウスには2ⅿほどに育ったバジルの灌木が並ぶ。ハウスの管理は、電気は風車の再生可能エネルギーで、熱源はバイマスボイラーで賄われている。その結果、寒さに弱いバジルも通年で収穫できるようになった。〝風のバジル〟と銘打ちブランド化に成功した。『壽』というバジル焼酎、そしてバジルソフトクリームがいま熱い。
寿都町名物のバジルソフトクリーム
著しい人口の減少 地方自治体が背負うツケ
片岡春雄町長のこれまでの町政20年間に人口は1200人減った。漁業や水産加工業などの地場産業はいまひとつ伸びない。小泉純一郎政権下で行われた地方交付税改革は、結果的に町の地力を奪っていった形だ。その中で寿都はもがいてきた。その結果が町営風力発電であり今回の文献調査への応募である。
私には、寿都の文献調査への応募は、相変わらず〝日本にオンカロはない〟と吠えまくる小泉氏への意趣返しのようにも映る。過去20年、小泉政治の不見識かつ無責任な政治の重いツケを地方が背負わされたのだ。それは何も寿都や神恵内だけではない。全国の地方自治体全てが同じ負の遺産を背負い込んでいる。
寿都の町中で聞いた話では、文献調査への応募からこれまでに、いわゆる反対派からは、北大OBの地質学者などが2度にわたって地層処分は危険であるとの論を披瀝する会合が催されたという。話を聞いても、語尾が全て〝こういう危険な可能性があるかもしれない〟という?(疑問符)で終わっていて、全く説得力がなかったとのこと。
一方、推進派の話は今までのところ一度もないという。政府・役所・事業者は一体何をしているのだろうか。これじゃあまるで三すくみの見殺し状態ではないか。
高橋・神恵内村長(左)と
全国から勇断にエール 問われる政治の決断
ただ、悪い話ばかりではない。文献調査への応募以降、寿都へのふるさと納税は増えているという。全国からこの町の勇断へのエールが集まっているのである。
全国には少なくない自治体がこの問題に手を上げようとしていることを私は知っている。どこの自治体も、今次の事態を受けて政府・役所・事業者がどう出ていくのかをじっくりと注視している。
今こそ政治の決断と実行力が求められているのではないか。そうすれば、この処分地問題は前に進む―その実感を寿都と神恵内の地を踏んで、ひしひしと感じた。