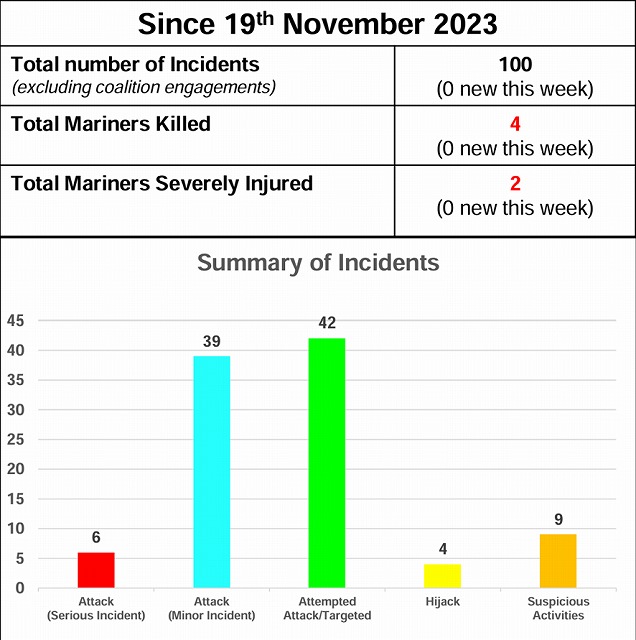矢島正之/電力中央研究所名誉研究アドバイザー
容量市場の一部として「長期脱炭素電源オークション」が2023年度から導入された。本オークションは、脱炭素化に向けた新設・リプレース等の巨額の電源投資に対し、長期固定収入が確保される仕組みにより、容量提供事業者の長期的な収入予見性を確保することで、電源投資を促進するためのものである。初回となる2023年度オークションの入札は2024年1月に実施され、4月26日にその約定結果が実施主体である電力広域的運営推進機関(OCCTO)により公表された。
長期脱炭素電源オークションは、大きく、「脱炭素電源」と「LNG専焼火力」があるが、前者は、募集容量400万kWに対してほぼ同レベルの401.0万kWが約定した(約定総額は年間2336億円)。後者は、募集上限600万kWに対して575.6万kWが約定した(約定総額は年間1766億円)。また「脱炭素電源」のうち「蓄電池・揚水」は、100万kWの募集容量を大きく上回る166.9万kWが約定した。これは「既存火力の改修(水素・アンモニア混焼)」区分などが募集上限に満たなかったため、余った枠が「蓄電池・揚水」に振り分けられたためである。また、蓄電池だけを見ると、落札109.2万kWに対して不落札が346.7万kWと激しい競争となったことが窺える。落札者で目立つのは、海外で実績を積んだプレーヤーで、電力関係者にとって初めて見る企業名が多かったようである。なお。原子力では、既設の中国電力島根原子力発電所3号機1件が落札している。
このような落札結果も踏まえて、長期脱炭素電源オークションのあり方について、様々な機関や識者から見解が述べられているが、以下では、筆者の考える本オークション制度の課題をいくつか述べたい。まず、「脱炭素化に向けた新設・リプレース等の巨額の電源投資に対し、長期固定収入が確保される仕組みにより、容量提供事業者の長期的な収入予見性を確保することで、電源投資を促進する」という本オークションの目的は達成されるであろうか。大型電源の建設を目指す事業者からの指摘にあるように、原子力、大型揚水、大型火力のような大型電源に関しては、リードタームが10~20年程度、総事業期間(各種調査から建設、運転、廃止まで)は、60~100年程度に及ぶため、収入やコストの変動リスクが大きく、投資の意思決定には慎重な事業性評価が求められる。
現段階で最善のコスト見積りをしても様々なコンティンジェンシーの発生で、コストが大きく上振れすることがあるだろう。税制や規制の変更によるコストの変化は、事後的な調整が認められるようになるかもしれないが、金利上昇、インフレ、為替変動など投資判断時点で予見できないその他のコスト変動要因のすべてを考慮した事後的調整を認めることは現実にはありえないだろう。そのような不確実性が存在する場合、応札価格を適切に設定することは、事業者にとって非常に難しいだろう。このため、大型電源の新設に関しては、投資に慎重になる事業者も少なからず存在するだろう。このことは、とくに建設から廃止措置に至るまで総事業期間が100年程度となる原子力発電の新設に関して当てはまる。
将来コストの不透明性が著しいのは、水素やアンモニアの専焼・混焼火力発電などの実証段階にある技術についてもいえる。本来、このような技術は信頼性、操作性、コストなどに関する実証試験を経て、初めて市場に出回るものである。実証段階の技術では、完成時のコストが当初見積りよりも、大幅に上振れするリスクは存在している。このため、大型電源の新設同様、実証段階の技術に関しても、応札価格を適切に設定することは、事業者にとって非常に困難となる可能性がある。このように考えると、従来の容量市場を補完して「容量提供事業者の長期的な収入予見性を確保することで、電源投資を促進するため」に導入された長期脱炭素電源オークションであるが、事業環境の一層の整備のために、制度の修正が必要になってくる可能性がある。
課題として次に指摘したいのは、脱炭素電源を導入する際に、設備や資源の調達に関して構築されるサプライチェーンの地政学的なリスクを考慮しなくてよいのかという点である。脱炭素は達成したけれども、設備や資源の供給が特定の国に大きく依存することにならないように、入札の条件や評価方法を工夫することが必要ではないだろうか。
最後に指摘したいのは、長期脱炭素電源オークションの対象外となった小規模再生可能エネルギー電源(10KW未満)の応札が可能となるような見直しが求められる点である。大規模脱炭素電源は膨大なコストがかかり、また将来コストの予測も難しいが、再生可能エネルギー電源は、長期的にコストダウンが見込まれ、将来的な拡大ポテンシャルは高い。このような再生可能エネルギー電源のポテンシャルを最大限引き出せるように、最低入札容量の引下げやアグリゲーションの要件緩和などにより、小規模電源でも応札しやすいような制度とする必要があるだろう。
電力自由化の綻びを繕うために、既存市場の補正や新たな市場の創設が絶えず行われてきたが、長期脱炭素電源オークションは、自由化の問題を解決する抜本的な処方箋となるだろうか。電力自由化は、いつまでも発展途上にあるのではなく、そろそろ完成されたものになってほしいものだ。
【プロフィール】国際基督教大修士卒。電力中央研究所を経て、学習院大学経済学部特別客員教授、慶應義塾大学大学院特別招聘教授、東北電力経営アドバイザーなどを歴任。専門は公益事業論、電気事業経営論。著書に、「電力改革」「エネルギーセキュリティ」「電力政策再考」など。