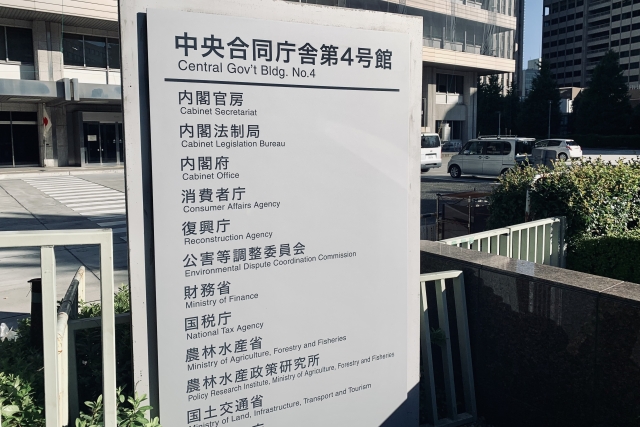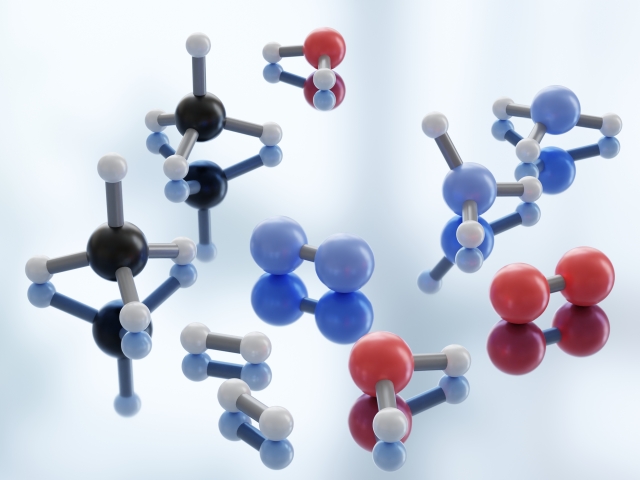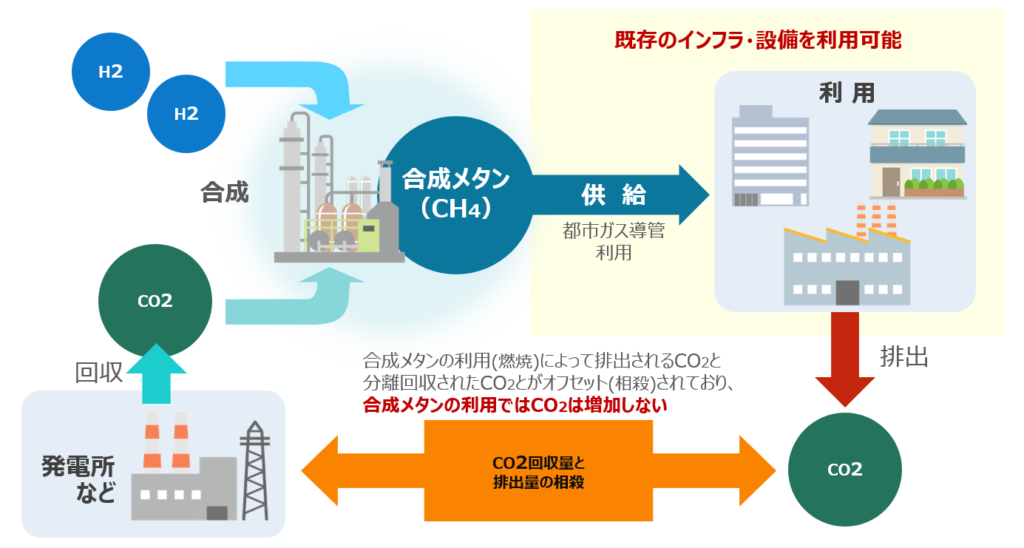◆「また若者が辞めた」の背景を考える
ある30歳手前の、理系の高学歴で優秀な青年が、電力会社を退社した。「もったいない」と私は思ったが、話を聞いた。
話を要約すると、以下の不満が勤務した電力会社にあったという。
▼滅私奉公の社風:会社の飲み会、地域社会との交流、企業組合の活動が、事実上強制される。新型コロナウイルス感染症の流行で、社外との交流、会社の飲み会が減って、ほっとした。
▼無駄だらけの業務:行政や地域社会に配慮し、仕事で安全確認と紙の書類が多すぎる。無駄を指摘して改善を提案すると、上司や周囲が不思議がり、「生意気」とレッテルを張られた。改善や業務を効率化しようという意欲が少ない職場で、やる気を出しても、何も現状を変えられない。
▼人事評価の不透明さ:年功序列で、上司の好き嫌いが人事に反映される傾向がある。自分は平均という、あまり良い人事評価は得られなかったが、再チャレンジしようとしてもそれが反映される兆しがない。
▼やりがいが見つからない:「電力を供給し、利用者を幸せにする」仕事と、社内で繰り返される。利用者を幸せにするといっても、研修や仕事で顧客対応の姿を見たが、へりくだりすぎていて、逆に嫌になった。自分は客の召使ではない。仕事の意味が書類や雑務の中で見えない。原子力事故の影響が続き収益が悪化。それに関係しない自分のいた部門も巻き込まれた。
電力会社を若くして退職した人のブログ
電力会社だけではなく、エネルギー産業はどこもよく似ているのかもしれない。
ただし、話を聞くと、筆者はこの退職した青年の考えから「甘え」のようなものも感じられた。どの会社でも、上記のような問題はあるだろう。
筆者は指摘した。「やり遂げたという達成感も成果もなく、また身についたと自分で思っている技量もないようだ。少し我慢することを考えた方がよかった。次を考えずに会社を辞めて、失敗したと悔やむ人はこの世の中にあふれている」。
すると、その青年は、「指摘はその通りだが、頭でわかっていても、実際に経験し、それによって嫌な思いをすると耐えられなくなった。特にほかの業界で働く大学院同期と比べると、ビジネスの経験での差が大きくなりすぎて悲しく、焦った」という。その気持ちは理解できる。次の仕事はまだ決めていないそうだが、この青年の未来に幸多かれと祈った。
◆波風を立てない組織のままでいいのか?
同じような指摘を、社内外の多くの人がする以上、電力産業に、何か問題があるのかもしれない。
電力・エネルギー産業は、「巨大装置産業」「行政の規制の影響が強い」「インフラであり安全な運営と安定供給が必須」「顧客は供給全地域の住民全員」という特徴がある。その特徴は、上記の退職した人の不満に思った会社の姿と密接にかかわる。
人に危険が及び、多くの人に影響を与えかねないエネルギー産業で、安全・安定供給に注力することは当然だ。安全の確保のためには、前例踏襲(ただし安全に運営されていた場合のみ)が、組織として最良の活動方法だ。そして「誰がやっても同じ結果」が求められるわけで、多少の改善はあっても、劇的な変化は組織として期待されないし、するべきではない。そうすると、波乱を起こさない社員の行動が望まれる。東電の原発事故のような大災害は別にして、大失敗はどの部署でもめったに起きないが、大成功も起きにくい。こうした組織では、年功序列で減点主義の人事評価に傾きがちだ。
前述の辞めた青年の不満は正しいようでもあるが、仕方のない面もある。しかし、ストレスがたまりやすい職場であることは確かなようだ。
◆変わらないままの業界、新しい問題を解決できない
ただしこのままでいいのだろうか。青年の叫びには、正しいことも含まれているように思える。
安定供給というこれまでの仕事の延長では、既存の電力産業、既存各社の対応は素晴らしい。今年の冬も含め、福島原発事故という危機を乗り越え、電力の供給を途切れさせず行ってきた。これは評価されるべきことだ。
ところが新しい動きがエネルギー産業を取り巻いている。自由化、東京電力福島事故の後の原子力への信頼の再構築、原子力発電所の再稼働、高レベル放射性廃棄物の地層処分などだ。そうした問題への対応は適切に行われているだろうか。これらへの対応でも、前述した「前例踏襲」とか「波風立てない」、「没個性」という態度で、電力会社は向き合おうとしているように思える。そして、筆者は、それらの対応に「すばらしい」という感想を抱けない。
一例を示してみよう。高レベル放射性廃棄物の地層処分の用地選定で、NUMOは日本全国で市民との対話イベントを重ねてきた。一度これを見学したが、まじめにやっている担当者の方には申し訳ないが、あまり面白くなかった。事実を説明しているのみだった。広告代理店の動員というのをやめてしまったので、この会合には数人しか出席せず、その多数が反対派という滑稽な状況になっていた。なかなか言えないことはわかっているが、一般の人たちに話をするには、話し手の顔が見え、そしてこの処分は住人の経済的利益につながることを打ち出すことが、印象に残る手法であろう。それを全くせず、金の話を意図的にぼかしているようだった。
つまり、電力会社のこれまでの社風、「前例踏襲」「とりあえず実行する」「波乱を起こさない」という特徴の延長の上で、こういう放射性物質の処分という新しい問題にも対応しようとしていた。効果が出ないのは当然だろう。
電力会社の人々は、自分を取り巻く社会環境の変化の必要を理解していると思う。しかし、実際変化に振り回され、自分が変わる必要を感じないと、対応する真剣度は低下してしまう。電力会社の持つ現場が多様で広すぎるために、状況の深刻さに気付いていない社員が多いのかもしれない。
◆会社の進むべき道‐批判者の声の中にある正しさを見つける
ルールを作り、仕事をやりやすく、効果を継続することは必要だ。前例踏襲も、多くの場合に仕事をスムーズにする。しかし、既存のルールの前提になる社会状況そのものが変わる中で、ルールを守り続ける行動は危険だ。そのルールは中の人しかわからない。それを変えていかなければ、まじめに仕事をしても、社会からずれ続ける可能性があるのだ。
前述の退職した若者を会社の中の人も、私のような外の人も批判することはたやすいだろう。けれどもその批判の中には、ルールそのもののズレとか、会社のあるべき姿そのものへの本質的な問題が隠れているかもしれない。
そして働く人が幸せになる職場は、組織を永続させる。この若者の言うような疑問を、多くの人が電力・エネルギー業界で感じているようだ。その問題点を発見し、是正することは長い目で見ると、会社のためになるはずだ。もちろん、全部を聞いていたら組織が動かなくなるが、必要な批判に聞く耳を持つべきかもしれない。
ルキノ・ヴィスコンティ監督の映画「山猫」(1963年)に、19世紀半ばのシチリアの老貴族に、美男俳優のアラン・ドロン演じる若い甥がイタリア統一運動に身を投じて「変わらず生き残るために、変わらなければならない」と話す場面がある。老貴族は、変化の必要を知りながら、「シチリアは変化を望まない、眠りにつきたがっているのだ」と政治参加の要請を固辞し、時代に取り残される道を選ぶ。この2つのセリフはいろいろなところで今でも繰り返されるが、電力業界の未来はどちらだろうか。
新しい変化を促し、それを気づかせるのは次の世代だ。辞める若い人の苦悩の中から、電力会社・エネルギー産業の変わる方向のヒントが見つかるのではないか。