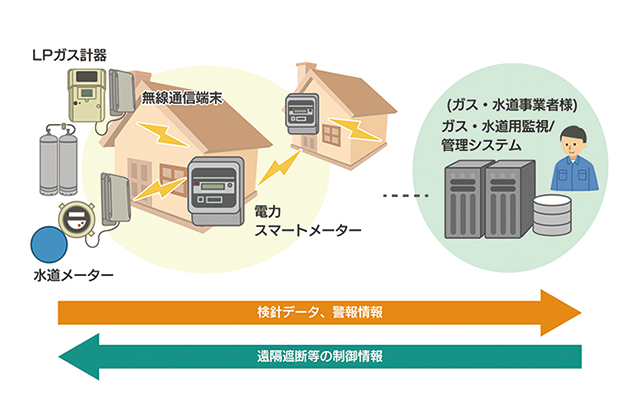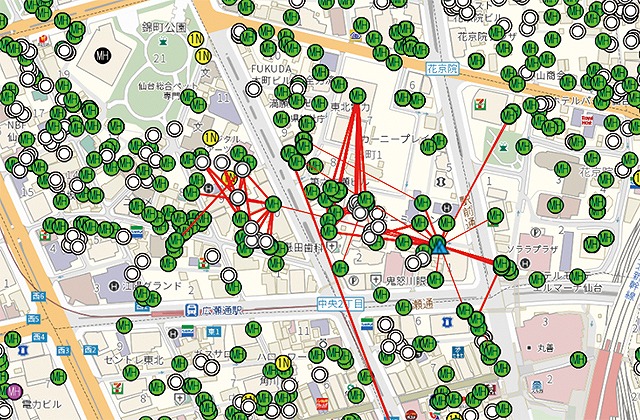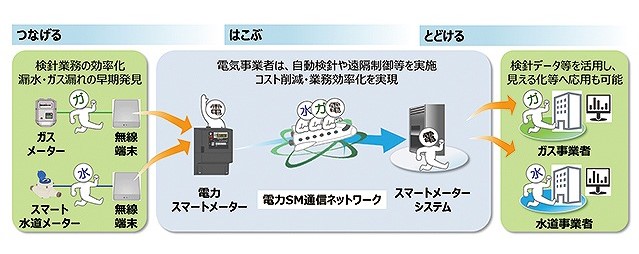【エネルギービジネスのリーダー達】秋田 亮/海幸ゆきのや社長
持続可能な社会の実現に向け、環境やエネルギーとともに大きな課題を抱える農業・食料分野。
「スマート養殖」で水産業に変革を起こそうとしているのが、関西電力系の「海幸ゆきのや」だ。

「Power to Food~でんきの力を食分野に~」をコンセプトに掲げて、静岡県磐田市でバナメイエビの陸上養殖事業を手掛ける合同会社「海幸ゆきのや」。関西電力発の農業・食料分野のスタートアップ企業として、2020年10月に発足した。
初代社長に就任した経営企画室イノベーションラボの秋田亮・副部長は、「農業・食料分野での事業化は関電として初の取り組み。エネルギーと情報通信の分野で培ってきた技術を掛け合わせることで養殖事業の最適化、高度化を図り、農林水産業・食料・環境を巡る社会問題の解決につなげていきたい」と狙いを語る。
養殖管理をAIで自動化 国産エビの安定供給を実現
事業開始に当たっては、IMTエンジニアリング(新潟県妙高市)の「屋内型エビ生産システム」(Indoor Shrimp Production System:ISPS)を採用。約1万6000㎡の敷地内に40m×12mの水槽を六つ設置し、稚エビから4カ月をかけて育成したバナメイエビを加工し、「幸えび」としてホテルやレストラン、スーパーマーケットなどに卸販売している。
世界的に水産物の需要が高まる一方で天然物の漁獲量が減少する中、陸上養殖には①適切な水質管理を行うことで、台風や赤潮といった気象条件に左右されない、②フンや残餌を含んだ養殖排水を海に排水することなく、環境への負荷が低い―など、海上養殖が抱える問題を解決しながら安定的に生産できるというメリットがある。実際、同社のプラントの生産効率は高く、一つの水槽に60万尾の稚エビを放流し、約45万尾を出荷することができる。
こだわりは、「安心安全」「美味しさ」「サステナブル」という三つの条件を兼ね備えたエビを育て出荷するということ。これを実現するのが、飼育条件や給餌、清掃計画といった養殖管理をAIで自動化する「スマート養殖」だ。
例えば、従来は育成開始時に、ゴマ粒ほどしかない稚エビを目視で数えなければならなかったが、同社のプラントでは画像を解析することで正確な尾数を把握できるシステムを開発・導入した。労働者の負担を軽減するだけではなく、給餌などの育成計画を精緻化し生産性を向上させることにも貢献している。
エビの育成に最適な養殖の仕組みは作り上げたものの、「当初は本当にうまく育つのか内心ひやひやだった」(秋田社長)。昨年11月に初めての出荷を迎えた時には、商品として自信を持って販売できるエビを育成できたことに胸をなでおろしたという。
テクノロジーの力を駆使 養殖業界に革命を超こす
関電入社後は、火力や原子力発電所の資機材調達に長く携わってきた。美浜発電所3号機の2次系配管破損事故が起こり、原子力安全が揺らぎかねない事態に直面した際には、下請け会社が技術やノウハウを維持できるよう、資金が循環する仕組みを作るなど、保全業務改革に腐心した。
電力マンとしてキャリアを積んできた秋田社長が、突如として農水産業に携わることになったのは、関電が19年3月に策定した中期経営計画の中で、少子高齢化や地域活性化といった社会課題解決に貢献し成長するために取り組む新領域の一つとして、農業・食料分野を掲げたことがきっかけだった。
早速、農業・食料分野に生かせる社内のアセットを探し始め、19年末には環境浄化の研究成果や発電所などを維持管理するためのデジタル技術をエビの養殖に活用できると思い至った。そして、20年2月には社の意思決定にこぎ着け、とんとん拍子に事業化の方向性が固まった。
ところが、いよいよ会社を立ち上げようという矢先に発生したのが新型コロナウイルス禍だ。実は事業化の前提として、年間生産される80tのエビを基本的には航空会社の機内食用に出荷する販路が見込まれていた。
コロナ禍で国際的な人の行き来が止まったことでその思惑は頓挫。そのため、養殖事業を開始する傍ら販路開拓にも苦心することになった。今後は、ECサイトなどを通じた最終消費者への直販を拡大するなど、これまでの水産業の慣例にない新たな販路の開拓にも意欲を見せる。
さらには、養殖業界に革命をもたらすべく、この陸上養殖システムを国内外に普及させることも視野に入れる。自ら事業に取り組まなくとも、関電が持つデジタル技術を含めた養殖システムとして提供することも考えられる。
「目指しているのは、次の社会により良いものを提供すること。テクノロジーの力で水産業の在り方に変革を起こし、やがて訪れるタンパク質クライシス(タンパク質の需要と供給のバランスが崩れること)に対応し、持続可能な地球環境や人々の生活につなげる必要がある」(秋田社長)。磐田市でエビの養殖を手掛けているのは、そのための第一歩なのだ。