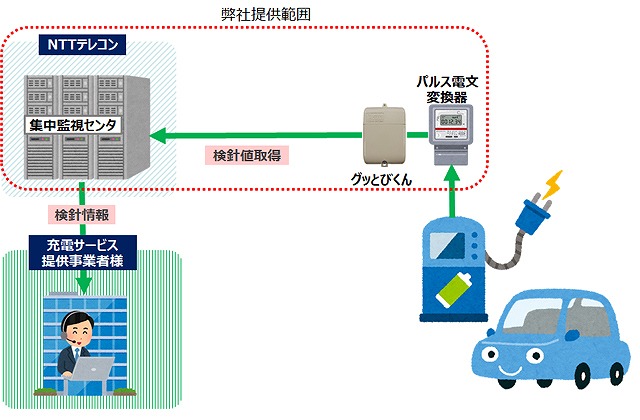【福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.2】石川迪夫/原子力デコミッショニング研究会 最高顧問
福島第一原子力発電所事故では炉心が溶融し、メルトダウンを起こしたといわれる。
だが、溶融炉心が圧力容器の底を溶かした事例は、軽水炉では確認されていない。
事故炉の廃炉は、一般の炉の廃炉とどこが違うのか。答えは簡単で、福島事故を伝える報道が常に伝えている。
「炉心が溶融してメルトダウンを起こし、発電所内部は爆発によって破壊された。強い放射能で汚染されている」と。一般庶民の理解はそれでよいのだが、廃炉関係者の答えとしては物足りない。
問題は「炉心が溶融してメルトダウンを起こし」のくだりだ。軽水炉では、溶融炉心が圧力容器の底を溶かしたという事例はまだ確認されていない。むしろ逆に、溶融炉心は圧力容器の中に残っている。溶融炉心がメルトダウンを起こすとは、必ずしも言えないのだ。
溶融炉心は底を突き抜けず 福島2号機も圧力容器内に
だが多くの人は、溶融炉心は高温であるから、流れ落ちて原子炉の底を突き抜け、格納容器の床も溶かして、放射能を周辺に放散すると理解している。これは大間違い、フェイクニュースの風評被害だ。事実を見てみよう。
福島第一の2号機は溶融したが、炉心は圧力容器の中に残っている。米国のTMI事故も同じで、溶融炉心の大部分は元の炉心位置にとどまっていた。以上二つの事例は、炉心溶融がメルトダウンを伴っていない明確な事実だ。
福島第一の1号機、3号機については後日述べるが、溶融貫通はまだ確かめられていない。
メルトダウンという外来語は、辞書を引くと「鋳つぶす」などとあり、コロナでおなじみのロックダウンと同類の強い意味を持つ言葉で分かり難い。
分かりやすいのは、反原発映画『チャイナシンドローム』だ。その粗筋は、炉心溶融事故によりメルトダウンが起きて格納容器の底に穴が開き、放射能が外部に放散されるというものだ。多くの人がメルトダウンを理解する原点がこの映画にある。
題名のチャイナシンドロームは、溶融炉心が地球を溶かし続けて反対側の中国に出るというブラックジョークが出所だ。
運が悪いことに、この映画の封切りの2週間後にTMI事故が起きたことから、映画は全米にセンセーションを巻き起こした。さらに、事故の発端をポンプの振動とした映画のストーリーがピタリと当たり、事故でも大きな振動がポンプに起きたことから、映画は事実として世間に受け止められた。
その影響であろう。原子力技術者の中に炉心溶融は圧力容器を溶かすと信じる人が多くいて、この「信仰」がマスコミを支配し、事故炉の廃炉を複雑にさせている。
読者には、軽水炉の炉心の溶融は必ずしもメルトダウンにつながるものではないという事実を、まずしっかりと頭に刻み込んでほしい。
炉心溶融=メルトダウンという信仰が、原子力技術者の間になぜ広まったのか。憶測だが、燃料の二酸化ウラン(UO2)の融点が2880℃と非常に高温であるところに根があろう。
大変な高温であるから、接触した物体は次々と溶けていき溶融は耐え間なく続くと考え、溶融で消費された熱は溶融炉心の崩壊熱が補ってくれるとの憶測が信仰の論理的根拠だ。
この安易な憶測は、原子力関係者であるが故に生じたものであろう。憶測は、輻射熱についての理解不足によるものだが、それは後日述べる。
チェルノブイリは溶融貫通 燃料棒が原子炉底に堆積
話を混乱させて恐縮だが、チェルノブイリ事故では、鉄筋コンクリート製ではあるものの、原子炉容器の底が溶融貫通しているのでその概要を次に述べる。
チェルノブイリ事故では、炉心火災が起きて炉内のグラファイトは全て燃焼(昇華)した。この火災は、インテルサット衛星からの映像を通じて、世界中の人が見ているから、間違いはない。
グラファイトが火災でなくなれば、空っぽになった原子炉容器に残るのは燃料棒だけだ。長さが7mもある長細い燃料棒は自立できないから、折れたり曲がったりして、最終的には原子炉の底にうずたかく堆積した。
堆積した燃料は、互いに崩壊熱で熱し合って、内部から溶融し始めた。溶融した燃料棒は温度が2880℃もあるから、厚さ約2mある鉄筋コンクリート製の原子炉底を溶かして、1階下のフロアに落下して築山を築いた。
築山の頂部には、次々と溶け落ちてくる溶融燃料とコンクリートの混合物で池ができた。池は3度氾濫したという。
 チェルノブイリ事故では原子炉容器の底が溶融貫通した
チェルノブイリ事故では原子炉容器の底が溶融貫通した
最初の2回の氾濫は、換気ダクトなどを溶かして、柱を伝わって流下しながら固化している。溶融ウランが混じった固化物、有名な象の足はその名残だ。
3回目の氾濫は溶液の粘度が薄かったらしく、50mも廊下を流れて床上で固化している。
ちなみに氾濫した溶液は、ウランを4~8%含んだコンクリートの多い混合溶液という。溶融燃料はコンクリートで薄まるのだ。
まとめると、溶融燃料は原子炉の底を溶かしコンクリートと混じって築山を作って固化した。池から氾濫した溶融物は、流下する過程で固化して、いずれも建屋の床を溶かしていない。
コンクリートとはいえ、原子炉の底が溶融貫通したのだから、メルトダウンが起きたといえる。だが、このメルトダウンは1度きりで、チャイナシンドロームもどきに格納容器(原子炉建屋)に穴を開けて放射能を放出していない。話が違うのである。
なお、溶融燃料がコンクリートを溶解できたのは、一つに黒鉛火災による原子炉の予熱があり、いま一つに融点2880℃という高温燃料の発する大きな輻射熱が、原子炉底の温度を1000℃程度の高温に加熱していたことが挙げられる。常温のコンクリートであれば、溶融したかどうか、疑わしい。
ここで余談を。旧ソ連は、事故直後にチャイナシンドロームの防止を真剣に考えたらしい。原子炉の下にメルトダウンの防止壁を作るために、炉心直下へ直行するトンネルの掘削を始めたことが記録されている。掘削作業が不必要と気付いて中止したのは後日のこと。相当掘り進めた後という。
この作業は映画チャイナシンドロームの妄想が作らせた、旧ソ連にとっては泣き面に蜂の無駄働きだ。現代の迷信であるメルトダウン信仰が作る妄想は、事故時の緊急作業まで狂わせた。ご注意を。
 いしかわ・みちお 東京大学工学部卒。1957年日本原子力研究所入所。
いしかわ・みちお 東京大学工学部卒。1957年日本原子力研究所入所。
北海道大学教授、日本原子力技術協会(当時)理事長・最高顧問などを歴任。
・福島廃炉への提言〈事故炉が語る〉Vol.1 https://energy-forum.co.jp/online-content/4693/