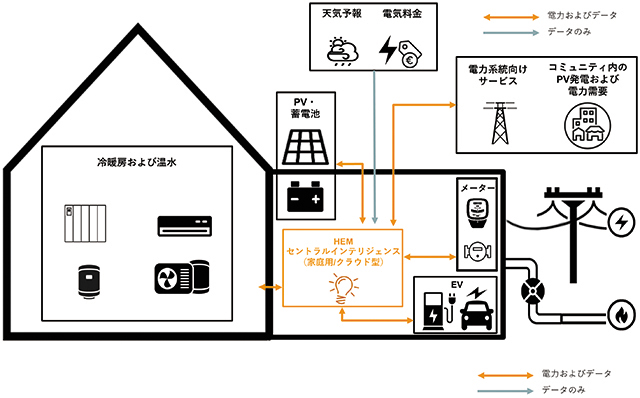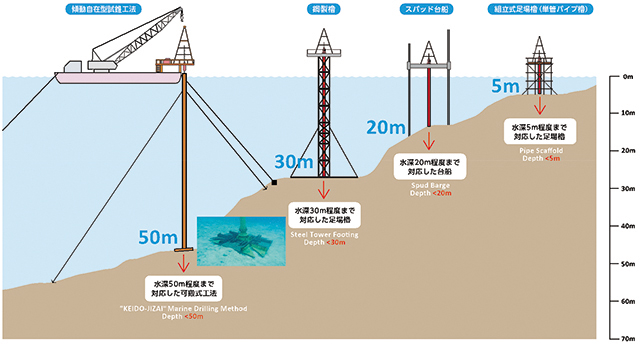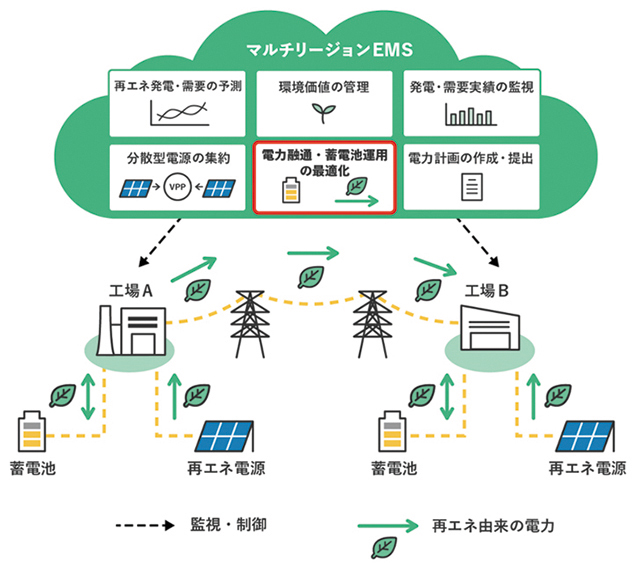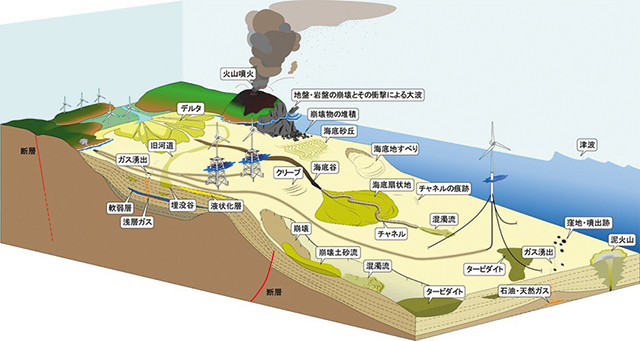【トキコシステムソリューションズ】
国内での水素利用は、トヨタ自動車の燃料電池車(FCV)「MIRAI」をはじめとした乗用車がけん引役となって始まり、水素ステーションなど関連施設の整備も進められた。現在、そうした動きに加え、トラックやトレーラーなど大型車両分野の開発・普及に向けた目標が設定されつつある。水素ディスペンサーにおいても、大型車両に合わせた高圧・大流量品の開発が始まっている。

こうした次世代品の開発を加速させるため、トキコシステムソリューションズは昨年9月、水素先端技術センターを開設した。設備には従来比5・5倍の吐出能力を有する圧縮機、同2・4倍の蓄圧器、同5・5倍の模擬充填タンクなどを導入。これにより、従来比3倍以上の大流量充填が実現し、乗用車など小型FCVでは3分程度、大型トラックでは10分程度で済ませる時間短縮技術や、1台のディスペンサーで乗用車とトラックなど異なるサイズの2台の車両に同時に水素を供給する充填技術、圧縮機や蓄圧器などのステーション機器の効率的な運転制御技術などの開発を手掛けている。さらに、出荷前試験の能力も従来の1カ月当たり最大6台から同20台へ引き上げた。
開発テーマのうち、FCVへの2台同時充填は、蓄圧器にためた水素をFCVタンクとの差圧を利用する。従来設備のまま2台同時に充填すると、タンクの圧力が低いFCVの方に水素が流れていき、先に充填しているFCVは待たされてしまう。設計開発本部の榧根尚之担当本部長は「圧縮機、蓄圧器の台数を増やせば解決するが、コスト増を最小限に抑えることが求められる。その解を見つけていく」と話す。
福島県で実施のNEDO事業 大流量ディスペンサー開発
このほか、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の「超高圧水素インフラ本格普及技術研究開発事業」にも参画する。昨年度、整備された「福島水素充填技術研究センター」(福島県浪江町)で、大型車両への大流量水素充填技術や計量技術の開発・実証を行っている。ここでも、大型車両への充填時間を短縮することを目指している。
「従来のトラックなどが軽油を給油するのにかかる時間と同等の所要時間がターゲットだ。大型車両向けでは、1台のディスペンサーから2本のノズルで同時充填する開発を進めている。これは従来のトラックが軽油を2本のノズルで給油しているのと同様の考えだ」(榧根氏)
大流量に向けては配管など周辺技術の開発も進める。エンジニアリングも手掛けるトキコならではの取り組みだ。FCVの普及には水素供給を支える設備側の取り組みも不可欠であり、同社から目が離せない。