脱炭素化、エネルギー安全保障の強化、自給率の向上、安定供給の確保……。
あらゆる観点から世界中で脚光を浴びている原子力発電。
わが国でも本格的なデジタル社会の到来を目前に、電力需要の急増が話題だ。
現行のエネルギー基本計画では依存度を「可能な限り低減」としているが、
岸田文雄政権下では「最大限活用」へと大きくかじを切った。
「原子力主力電源化」が徐々に現実味を帯びてきた格好だ。
再稼働の加速や新増設の実現に向けて乗り越えるべき課題をあぶり出し、
国益に資する原子力政策の在り方を探る─。
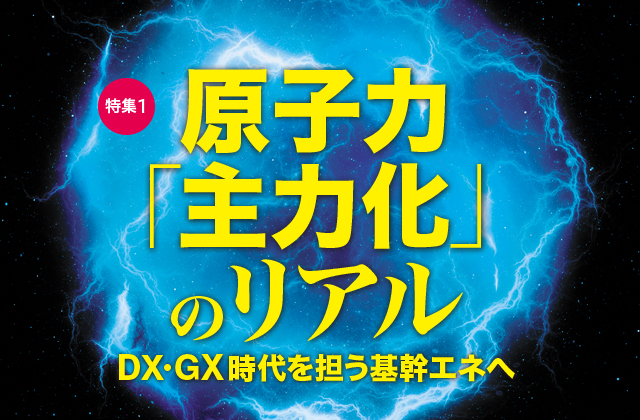
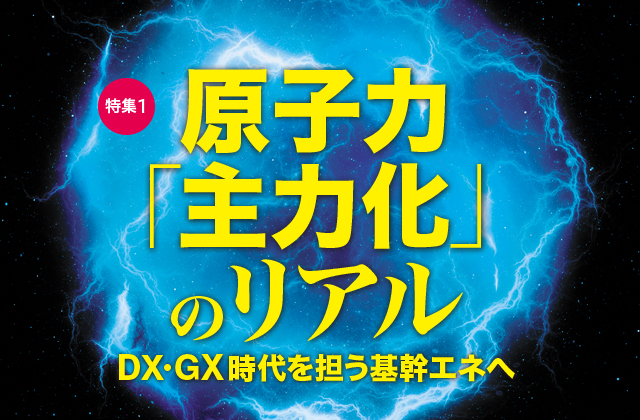

脱炭素化につながる水素やアンモニアといった次世代燃料を発電や産業用途で生かす―。大手電力各社がそんな近未来を視野に入れた取り組みで存在感を発揮している。その一社が、東京電力ホールディングスと中部電力が折半出資するJERAだ。同社は火力発電で使う燃料の一部を、石炭から燃やしてもCO2を出さないアンモニアに置き換えて発電する大規模な実証試験で有効性を確かめた。多様な業種を巻き込んだ脱炭素燃料のサプライチェーン(供給網)づくりも全国各地で活発化する中、最新動向に迫った。
発電時にCO2を排出しない「ゼロエミッション火力発電」の実現に向けた大きな一歩を踏み出したのがJERAだ。同社はIHIと連携し、碧南火力発電所(愛知県碧南市)4号機で発電燃料の20%(熱量比)をアンモニアに転換する試験を、4月から6月にかけて実施。定格出力100万kWで運転を行った結果、転換前との比較で窒素酸化物(NOX)は同等以下、硫黄酸化物(SOX)が約2割減少したことを確認した。

試験で良好な結果が得られたことを受けて今後は、ボイラーや周辺機器への影響などを詳細に調べる活動を進め、2025年3月までにアンモニア転換技術を確立することを目指す。
船から荷揚げした液体のアンモニアは、発電所内のパイプラインを経由して専用のタンクに貯蔵。そのアンモニアを気化し、石炭を燃やすボイラーに差し込まれたバーナー(燃焼装置)に送る。そこで生まれた熱で水を沸かして蒸気に変え、タービン発電機を高速で回して電気をつくるという仕組みだ。
早ければ27年度に4号機で商用運転を実施。将来的には国内の石炭火力発電で、アンモニアへの転換率を30年代前半に50%以上、40年代までに100%へと段階的に引き上げていくことを視野に入れている。
火力発電の燃料を石炭から燃焼時のCO2排出量がより少ない液化天然ガス(LNG)へシフトし、さらに石炭やLNGを徐々にアンモニアや水素に転換することで、エネルギーの安定供給を果たしながら脱炭素化を実現していく―。そんなシナリオを描くJERAは、国内で培った技術や経験を海外に展開することも目指す。

─アンモニアや水素など新燃料への取り組みの現状をどう見ていますか。
廣田 カーボンニュートラル(CN)社会を実現する上で、水素やアンモニアを燃料として活用していくことは非常に重要な取り組みです。発電燃料としてはもちろん、輸送や工場のボイラーの熱源といった電化できない工業プロセスの脱炭素化に向け鍵となる燃料であり、既にさまざまな業種の企業がコンソーシアムを組みながら取り組みを始めています。
─エネルギー利用に向けての課題は。
廣田 燃料として活用するためには、水素にせよアンモニアにせよ、膨大な量を必要とします。現段階でそれを賄えるような大規模な製造・生産の事業例はなく、世界中で燃料のスケールに合った技術やシステムの確立を目指し開発が進められています。技術面に加えて、プロジェクトに対し、きちんとファイナンスが付くかどうかも大きな課題です。ファイナンスが付くためには、製造した水素・アンモニアを安定的に買い取る需要家の存在が欠かせません。燃料規模のプロジェクトを立ち上げるには、技術とファイナンスの二つの課題をうまくクリアしていく必要があります。
─そうした課題に対する政府の支援策とは。
廣田 今年5月に水素社会推進法が成立し、施行に向け準備を進めています。この中に、化石燃料との価格差に着目した支援が盛り込まれています。支援期間は15年ですが、その後も10年間供給を継続する計25年間の事業計画を立ててもらうことで、長期的なプロジェクトを成立しやすくする狙いです。また、海外から燃料を受け入れる拠点整備に対しても支援を行います。詳細な制度設計はこれからですが、燃料の供給、拠点整備の双方を支援することで、16年目から経済的に自立可能なサプライチェーンの構築を目指します。
─企業に対しては何を期待しますか。
廣田 今後、CNの実現を目指していくわけですが、同時に、企業は新しいビジネス機会を捉えて成長につなげるという視点を持たなければなりません。CNにより、足元のコストが増える側面はありますが、いかにコストを抑制するかだけではなく、新たな市場に向け、稼げる製品と稼げるサプライチェーンを作ることを両輪で考えていかなければ、取り組みは持続しません。増えるコストは、新しい成長市場に進出するための「投資」であるという考えを持ち、トランスフォ―メーション(X)に挑戦していただきたいと思います。政府としても、Xに挑戦する企業に対しては、思い切った支援を行っていきます。
ひろた・だいすけ 2005年東京大学大学院電気工学修士を修了、経済産業省入省。原子力・石油ガス政策、新型コロナ下の予算編成・税制改正やGX政策などを担当。24年7月から現職。

橘川 GX(グリーントランスフォーメーション)の基本方針に沿って、今年5月に水素社会推進法とCCS事業法が成立し、制度が着々と整ってきています。そうした中、水産・アンモニア拠点の整備支援の公募が始まり、10件が一次審査を通過しました。一見するとアンモニアと水素がほぼ半々ですが、値差補填の比率を見ると、アンモニアが高くなっていて、そこに若干、e―メタノールが入ってくる流れになっているのが現状です。
村木 グローバルでの水素利用はヨーロッパ、アメリカが中心で、基本的にはグリッドに供給できない域内の再生可能エネルギーの余剰分を水素に転換してパイプラインに入れています。一方、アジアはパイプライン網がなく、再エネと水素需要が結びつきにくい。日本、韓国、シンガポールではアンモニアを輸入して直接利用、もしくはアンモニアをクラッキングして水素供給する動きが出てきています。また、日本と韓国は、石炭火力発電所の燃料転換から始まり、石炭火力のないシンガポールではアンモニアガスタービンを入れる準備が進んでいます。
橘川 水素やアンモニアといった次世代燃料の普及は、オフテイカー(引き取り手)次第ということが明確になってきました。オフテイカーは石炭火力発電所、船、飛行機の3種類です。この中で、都市ガス会社がオフテイカーとなるe―メタンは、都市ガスとして使う場合、熱量を45MJから40MJに下げる必要があります。徐々に下げると多くのコストがかかるので、一気に下げる点が課題です。
村木 旧一般電気事業者、IPP事業者で具体的な動きがあるのは、今回の長期脱炭素電源オークションにおいて、アンモニアへの燃料転換に手を挙げているのが、北海道電力の苫東厚真、コベルコパワー神戸の2基。それからJERAの碧南火力の2基です。中でも、碧南火力の大規模実証の成功は、大きなインパクトでした。

橘川 今でも世界の30%以上の電源が石炭で、天然ガスの約1・5倍あります。碧南火力は、新興国がカーボンニュートラル(CN)化を実現できるモデルになりますね。
村木 東南アジアでは、稼働年数の少ない石炭火力が多く、地域の雇用にも重要な役割を果たしているので簡単にはやめられません。一方で、天然ガス火力に切り替えると、インフラ整備にコストがかかる上に、水素インフラも作らなければゼロエミッションにはなりません。そこで、われわれは一回のインフラ投資でゼロエミッションが達成できるよう、石炭火力でのアンモニア導入からアンモニアガスタービンによるゼロエミッション化を提案しています。
橘川 アンモニアの世界において、日本は世界のボスになれそうですね。あと、CCS(CO2回収・貯留技術)でのアンモニア利用も考えられます。村木さんにご案内いただいたアメリカのアンモニア工場では、CCSが行われていました。
村木 アメリカのテキサス州、ルイジアナ州では、天然ガスが産出され、アンモニア工場が立地していて、CCSのフィールドもある。近くにインフラが集中しています。日本は、CO2の発生源とCCSを実施するフィールドが離れているケースが多く、インフラ形成を含めたコストが課題です。。
橘川 そうした中、苫小牧では出光興産の製油所の敷地からCO2を海底に直接入れています。このような好条件は、世界中を見てもなかなかありません。
村木 アンモニアの輸入インフラ形成に関して、周南では出光がLPGタンクをアンモニア用に切り替えて利用する計画です。アンモニアの液温度はマイナス33℃と、LPGと同じ温度帯なのでタンクの転用が可能です。三菱商事は波方LPGターミナルでも同様の計画を進めています。JERAは碧南で大型タンクを新設する計画で、日本のLNGタンクに多く採用されているプレストレストコンクリート(PC)で外側を巻き、液漏れのリスクのないタンクを建設する計画です。
化学品や肥料用途向けのアンモニア・トレーディングに1960年代後半から関わる三菱商事。インドネシアでは年産70万tのプラントを持つ企業に出資するなど、生産から利用にいたる知見を重ねている。そうした中、同社はアンモニアをエネルギー燃料として新たなサプライチェーンを構築しようと動き出している。上流では、米ルイジアナ州レイクチャールズで出光興産や、メタノール製造の世界大手、スイス・プロマン社と組みながら、2030年までに年間約120万tのアンモニア生産プロジェクトを検討。このプロジェクトでは、関西電力と三菱重工業が共同開発したCO2回収の国産技術などを採用し、CCSを行いながらクリーンアンモニアをつくる構想だ。
輸送先は当然、国内向けを視野に入れる。その際、鍵を握るのが国内供給インフラの整備と利用先の確保だ。「供給インフラ面では、当社が愛媛県で保有するLPガス輸入基地、波方ターミナルの既存設備の存在がポイント」(次世代エネルギー本部の村尾亮一・次世代発電燃料事業部長)。LPガスとアンモニアは物性としての組成が似ており、既存インフラとこれまでの運用ノウハウを生かすことで、早く安全にアンモニア転用できるからだ。そうした利点を踏まえ、波方拠点の整備を進める。
さらに上流で協業する出光興産とは、出光が推進する周南コンビナートアンモニア供給拠点事業との連携も視野に、アンモニア普及の協業を構想している。
波方拠点を経由する利用先としては、四国電力と検討し石炭火力向け燃料利用を模索する。また、広島県の自動車メーカー、マツダとも協力する。地元工場で稼働している大型コージェネの燃料をアンモニアへの完全転換を模索する。もともと同社とマツダとは、工場向けエネルギー供給の事業会社を共同出資して立ち上げた経緯がある。そんな関係を生かしながら、アンモニア利用の新しいスキーム構築に奔走している。

米国テキサス州・ヒューストン港で、低炭素アンモニア事業の本格展開に向け動き出しているのがINPEXだ。
エア・リキード(AL)、LSBインダストリーズ、VMHの計4社でコンソーシアムを組成。天然ガスを原料に水素を製造し、2027年までに年間110万tのアンモニアを商業生産する計画だ。ALの空気分離装置やCO2回収技術を組み合わせながら効率的に水素やアンモニア転換を図り、CO2を地中に埋める。
さらに、VMHが運用している既存のアンモニアターミナルを活用し、LSBの製造ノウハウと販売網を生かす。4社は、すでに事業化調査を終えており、概念設計も間もなく完了する。
同社水素・CCUS事業開発本部事業推進ユニットの神谷剛人ジェネラルマネージャーは、「水素とアンモニアの事業会社をそれぞれ設立する予定で、いずれにも当社が主導的な役割を担う。海外における低炭素事業で日本企業が製造から販売まで主導するユニークな取り組みになる。販売先は、アジアを中心としてエネルギー用途を想定しており、欧州も視野に入れている」と説明する。
同社は新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)やエネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の協力を得ながら、米国の「ミニチュア版」ともいえる取り組みを国内でも実証事業として行っている。
新潟県柏崎市の自社ガス田を生かして、天然ガスから水素をつくる。その際に出るCO2をEGR(排ガス再循環)としてガス田に注入し、CCUSを行いながら天然ガス生産を促進する。その天然ガスから年間700tの水素を製造し、うち100tをアンモニアに変換する。水素は水素エンジンを通して発電する計画で、規模は小さいが、生産から利用までの「一貫実証」は日本で初めての取り組みとなるという。
この工程で注目すべきことがある。それは新しい技術を使ってアンモニアを生産することだ。ベンチャー企業、つばめBHB社が生み出した新触媒を用いることで、低温低圧での生産が可能になる。「従来のハーバー・ボッシュ法とは異なる手法で、小規模でも効率的な生産が可能になる。新しい製造手法を用いることで国内の技術革新にもつなげていきたい」(同)
25年から生産を始める計画で、実証後はその成果を活用し新潟県内で既存のインフラを活用したブルー水素製造プラントを建設し、30年までに商業化を目指している。
これまで中東やオーストラリアを中心に、石油やLNGの生産・販売をコア事業としてきた同社にとって、「アンモニア」は未知の領域だ。エネルギー利用を目指すなら安定生産と安定供給が至上命題。これまで化石資源で培ってきた知見を生かしながら、アンモニアの安定的なハンドリングに向けて、同社の腕が試される。

三井物産は、水素・アンモニア戦略の中で、燃焼時にCO2を排出しない「クリーンアンモニア」を脱炭素社会の実現に役立つ次世代燃料の有望な選択肢の一つと位置付け、国内外で調達先の開拓やサプライチェーン(供給網)づくりに力を入れている。同社は、経済成長が著しいアジア市場などを舞台に約50年にわたりアンモニアの取り扱い実績を積み上げてきた。その間に蓄積した経験や知見を生かしてアンモニアの利用拡大を後押ししたい考えだ。
日本政府は「グリーン成長戦略」の中で、2050年に「世界全体で1億t規模を日本がコントロールできる供給網を構築する」という目標も掲げた。
三井物産はこうした目標の達成を後押ししようと、クリーンアンモニアの製造から輸送・利用・販売にいたる一連のプロセスに参画している。ベーシックマテリアルズ本部メタノール・アンモニア事業部クリーンアンモニア事業開発室長の高谷達也氏は「これまでアンモニアを扱ってきた化学品セグメントと、エネルギーセグメントが連携してシナジー(相乗効果)を発揮し、脱炭素社会への移行期に貢献したい」と意欲を示した。
米国では、窒素系肥料最大手CF Industries Holdings(米イリノイ州)との間で、窒素と化石燃料由来のブルー水素を合成した「ブルーアンモニア」の事業化に向けたFS(実現可能性調査)を進めることで合意し、22年7月に共同開発契約を締結。24年後半のFID(最終投資決断)を目標に準備を進めている。メキシコ湾で年間120万t規模の生産を目指す。
5月には、アラブ首長国連邦(UAE)のアブダビ国営石油会社(ADNOC)グループや韓国のGSエナジーと連携し、UAEでアンモニア製造プラントの建設を開始。27年に生産を始めるとともに、追加設備を導入して製造過程で排出されるCO2を回収・貯留し、30年までにクリーンアンモニアの製造を開始する予定だ。
三井物産は、国内各地で計画するアンモニア供給事業にも協力している。例えば、三井化学やIHIと手を組み、大阪堺・泉北工業地域にアンモニア供給拠点を設けるとともに、関西・瀬戸内エリアを含めた広域の需要地に供給網を形成。3社はこうした取り組みの実現に向け、経済産業省の「非化石エネルギー等導入促進対策費補助金(水素等供給基盤整備事業)」に応募し、5月に採択された。
「燃料の生産国と需要国が事業上のリスクをシェアし、協力的な関係で仲間づくりを進めていかなければ、安定成長する新エネルギー市場が育たない」とエネルギーソリューション本部水素ソリューション事業部水素マーケット開発室長の天野功士氏。豪州では、1万kW規模のグリーン水素製造設備の建設を進めている。総合商社の強みを生かし、各国・地域の需要や制度の動向を見極めながら、クリーンアンモニアに加えて水素市場も段階的に攻略する方針だ。

三菱重工はカーボンフリー燃料として水素・アンモニアを利用するガスタービンの開発に注力する。水素ガスタービンの早期商用化に向けては同社高砂製作所内に「高砂水素パーク」を整備、水素の製造から発電までにわたる技術を一貫して検証している。
水素ガスタービン開発では昨年11月、実証発電設備で最新鋭の「M501JAC形」ガスタービンによる水素30%混焼運転に成功した。今後、中小型ガスタービンは25年、大型ガスタービンは30年以降の水素専焼での商用化を目指し、新型燃焼器の開発を進めていく。
水素は天然ガスに比べて燃焼速度は7倍と高く、燃焼器で天然ガスと水素を混焼、または専焼すると、天然ガスのみを燃焼した場合よりも火炎位置が上流に移動し、空気と十分混合する前に高い火炎温度で燃えるため、NOXが増加する。また、燃焼器の上流に火炎が遡り、逆火が発生するリスクも高くなる。そうした課題を解消するため、専焼用のマルチクラスタ燃焼器では混焼用燃焼器より、高流速かつ混合距離が短縮可能で、逆火耐性が高いものを目指す。また、火炎を多数に分散することでNOX低減を図る。
一方、アンモニアは天然ガスに比べて発熱量が3分の1、燃焼速度が5分の1と低いため、燃焼が不安定になりやすく、火炎を安定して保持することが難しい。また、窒素分を含んでいるため、燃焼の過程で発生するフューエルNOX(燃焼由来)が生成されるため、NOXを低減する手法が必須だ。そこで同社はアンモニア燃焼システムとして、直接燃焼GTCC(ガスタービン複合発電)と分解GTCCの2方式を検討中。直接燃焼GTCCはNOX排出量を低減するアンモニア用燃焼器と高効率脱硝装置を組み合わせた。同システムは中小型H-25形ガスタービンで開発を進め、25年以降の実機運転、商用化を目指す。分解GTCCは実用化を検討中だ。
長期脱炭素電源オークションに参加するうえで、火力発電の次世代燃料への対応は必須条件となる。こうした発電ニーズに三菱重工はさまざまな開発を進めて応えていく構えだ。

エネルギー安定供給という使命の下で、石油や天然ガスの探鉱・開発・生産の技術を長年にわたり培ってきた石油資源開発(JAPEX)。そんな同社が挑戦する舞台が広がっている。一つがカーボンニュートラル社会の実現を後押しする取り組みで、アンモニアのサプライチェーン(供給網)づくりに積極的に関与している。
化学や機械の関連企業が集積する福島県相馬地区。太平洋に面する同地区は港湾機能にも恵まれている。その地でJAPEXは三菱ガス化学、IHI、三井物産、商船三井と連携し、アンモニア供給拠点の構築に向けた共同検討に乗り出した。資源エネルギー庁が実施する「非化石エネルギー等導入促進対策費補助金(水素等供給基盤整備事業)」の公募に参加し、5月に採択された。
共同検討では、海外から輸入した低炭素燃料の「クリーンアンモニア」を相馬地区の拠点に受け入れて貯蔵し供給するための調査を進めるとともに、需要調査にも取り組む計画だ。
アンモンニアを発電用燃料として生かす可能性を探るとともに、化学品原料などの工業用途も想定。こうした取り組みで関東以北の広域圏に「脱炭素の輪」を広げることで、地域経済を活性化する一助を担いたい考えだ。水素社会の本格到来も見据え、アンモニアを「水素を運ぶ手段」として生かす可能性を探索することにも意欲を示している。
日本政府は、2030年までに燃料としてのアンモニアを年間300万t導入する目標を掲げている。JAPEX国内カーボンニュートラル事業本部事業一部の山之内芳徳部長は、政府目標の達成に貢献するため、「アンモニアを長期で使ってもらえるよう需要を開拓し、競争力のある価格で届けられるアンモニア供給基地を実現したい」と強調。LNG基地などの輸送・供給インフラを地域密着で運営してきた実績も生かし、30年の操業開始を目指す。
JAPEXは、海外市場での事業展開も狙っている。その一例としてカナダのアルバータ州で、同州政府の投資誘致機関Invest Alberta Corporation(IAC)と協業する覚書を締結。IACの協力を得て、発電や工場などから排出されるCO2を回収・貯留(CCS)して有効利用する技術「CCUS」や、バイオマス発電とCCSを組み合わせた「BECCS」、化石燃料由来の低炭素燃料「ブルー水素・アンモニア」の事業創出を目指す。
21年には、カーボンニュートラル社会の実現という政府の宣言を踏まえ、総合エネルギー企業としての方向性を示す「JAPEX2050」を策定。カーボンニュートラル社会づくりで果たす責務と注力分野を明確に示した。
CCSとCCUSの早期事業化を目指すことに加えて、ブルー水素など周辺分野への参入を視野に入れる方針も盛り込んだ。JAPEXの展開から今後とも目が離せない。

─CO2を回収して地下に貯留する技術「CCS」がカーボンニュートラル社会づくりで果たす役割について教えてください。
北村 発電分野では、化石燃料から脱炭素化につながるクリーン燃料への転換を進めることでCO2排出量を減らしていく過程で、「つなぎ」の役割を果たすのがCCSです。その転換期には、化石燃料を燃焼して取り出すブルー水素やそれに窒素を合成してつくるブルーアンモニアが発電で必要となりますが、いずれ再エネ由来に置き換わるでしょう。そうなると発電向けCCSの位置付けも変わります。ただ、鉄鋼や化学などエネルギー集約型産業の脱炭素化は難しく、非発電分野向けCCSは将来も使われ続けると見ています。
─日本が脱炭素化に貢献するためには、どの程度のCO2貯留量が必要ですか。
北村 2050年時点で年間約1.2億~2.4億tのCO2貯留が必要という推計があります。それを達成するためには、50年までの20年間、CCS事業を毎年立ち上げ、約600万~1,200万tずつ年間貯留量を増やさなければなりません。そこで政府は環境整備を進め、30年以降にCCS事業を本格展開することを目指しています。JOGMECは政府と緊密に連携し、そうした取り組みを支援します。
─政府の「CCS長期ロードマップ」に沿って力を入れている取り組みは何ですか。
北村 横展開可能なビジネスモデルで規範となる先進プロジェクトを支援する「先進的CCS事業」です。23年度に始めたもので、初年度に7案件を選定しました。24年度も発電や石油精製、化学、鉄鋼など多業種の事業者が参画するプロジェクトとして、9案件を選びました。5月には、CO2を埋める地層の試掘や貯留の許可制度を盛り込んだ「CCS事業法」が成立しており、事業化に向けて大きな一歩を踏み出したと言えます。
─事業化に向けた課題も抱えています。
北村 CCSの実施地域に与える影響を踏まえて、住民理解を得ることが大切です。貯留の適地である枯渇した石油・ガス田は国内では量的に限られることも課題で、日本で回収したCO2を海外に輸送し貯留する手法が解決策となります。今年度の先進的CCS事業の対象案件のうち4案件は海外貯留でした。法制度が進むCO2受け入れ国も限られる中、世界で環境整備や政府間協議が進むことを望んでいます。先進的CCS事業には、地下水で満たされた地層「帯水層」をCO2の大規模貯留に向く貯留先として役立てる調査も含まれており、今後の展開に期待しています。

きたむら・りゅうた 東京大学工学部卒業後、1995年石油資源開発入社。2007年JOGMEC入構。シドニー事務所勤務などを経て、24年から現職。
2026年11月、国産エンジンを搭載し、アンモニアを燃料とする「アンモニア燃料アンモニア輸送船」が完成する。この世界初の取り組みは、海洋分野における脱炭素化実現に向けた大きな一歩になると期待されている。「日本の技術で海と未来を変える」を合言葉にこのプロジェクトに参画しているのは、日本郵船、ジャパンエンジンコーポレーション、IHI原動機、日本シップヤード、日本海事協会の5社のコンソーシアムだ。日本の船級協会として一世紀以上にわたり船舶の安全性を第三者として証明してきた日本海事協会は、このアンモニア燃料アンモニア輸送船の安全性評価を担当している。
プロジェクトが担う役割は四つある。
第一が、国際海運のネットゼロ・エミッション達成に向けた取り組みをリードすること。燃焼してもCO2を排出しないアンモニアを使用したアンモニア輸送船の開発・建造を通じ、アンモニアを燃料とする船舶の実用化を推進していく。
第二がアンモニアバリューチェーン(価値連鎖)の構築だ。アンモニアの用途は、従来の化石燃料から火力発電所の混焼などへと移行し、需要が急増すると想定。アンモニアを効率的に幅広く供給できるバリューチェーン構築を促していく。
第三に、日本海事産業の強化だ。海洋国の日本にとって海事産業の繁栄は、経済安全保障上重要だ。ネットゼロ・エミッション実現に向けた燃料転換を好機とし、日本を代表する海事産業企業の技術力を集結し、高い環境性能と安全性を備えた船舶を他国に先駆けて供給することを目指している。
第四に、船舶燃料としてのアンモニアに関する国際ルール化だ。現状、IMO(国際海事機関)は、アンモニアを船の燃料としては認めていない。国際ガイドラインも未整備だ。日本海事協会が国土交通省と連携し、コンソーシアムを通じてアンモニア燃料船舶の開発に関与することで得られた知見をIMOに提供することで、アンモニア燃料船の議論をけん引する構えだ。
技術部の酒井竜平氏は「何を基準に安全であるとするのか、『安全のコンセプト』を定めていくことが非常に難しい作業だった」と語る。例えば、アンモニアを通す導管は漏洩防止のために何重に覆うのが適切なのかという課題一つを取ってみても、考慮すべきことは多くあった。
日本海事協会は、プロジェクトを通じて得られた専門的知識を国交省海事局に提供してきた。その貢献が実を結び、今年12月、アンモニア燃料船に関する初めての国際ガイドラインが発表される予定だ。四方を海で囲まれ、資源や食糧のほとんどを輸入に頼る日本にとって、日本が策定までリードしてきたガイドラインは、海事産業がさらなる発展を目指す際に大きなアドバンテージとなるだろう。

IHIは、約10年にわたり磨いてきたアンモニアの燃焼技術を生かし、火力発電の脱炭素化を後押ししている。アンモニアを燃料として活用することで、発電設備から排出されるCO2の削減に貢献したい考えだ。
IHIは持続的な高成長に向けて2023年度に打ち出した「グループ経営方針2023」で、クリーンエネルギー分野を「育成事業」と位置付けた。この方針に沿って、アンモニアの製造から貯蔵・輸送・利用にいたる「バリューチェーン(価値連鎖)」の構築事業に積極的に参画。下流では、「電力」「船舶」「産業」という三つの用途を視野にアンモニア燃料の利用技術開発に力を入れている。
存在感を発揮した舞台の一つが、JERAが運営する碧南火力発電所(愛知県碧南市)4号機だ。両社は燃料である石炭の20%をアンモニア燃料に置き換えて発電する大規模な実証試験を4月から6月にかけて進めてきた。
実証で使うバーナー(燃焼装置)を開発したのがIHIだ。5号機で22年に進めたアンモニア燃料の小規模利用試験で得られた知見を、実証用バーナーの開発に役立てた。実証では、ボイラーに差し込まれた石炭焚きバーナー48本をアンモニア混焼用に改造して実施。同発電所に受け入れた液化アンモニア燃料をガス化した後にボイラーに送り込み、バーナーで石炭と同時に燃焼させる仕組みだ。
実証を通じて,燃焼により発生する窒素酸化物(NOX)や未燃分などの燃焼特性に加えて、硫黄酸化物(SoX)やCO2などの環境特性も確認。アンモニア混焼の有効性を実証したという。
アンモニア転換の量をさらに引き上げると、こうした環境特性と燃焼の安定化を両立するハードルが高まる。IHIは引き続き燃焼技術の高度化を追求し、転換率50%以上の達成に貢献。将来的には、アンモニアのみで燃焼するバーナーを開発し、アンモニアのバリューチェーンづくりに弾みをつける。資源・エネルギー・環境事業領域カーボンソリューションSBUの難波裕二次長は「日本で先行的に磨いたアンモニアの利用技術を周知し、アジアにも広げていきたい」と意欲を示した。
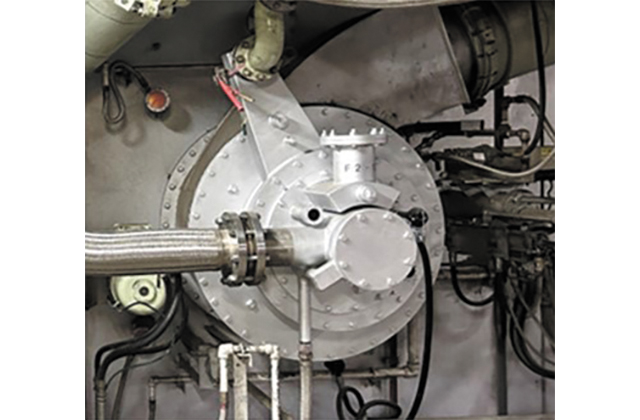
佐賀市の清掃工場で発生する排出ガスからCO2を取り出し、地元の農業に生かす―。そうした仕組みが地域の脱炭素化と資源循環を促す取り組みとして、国内外から熱い視線が注がれている。東芝エネルギーシステムズ(東芝ESS)が火力発電所で磨いたCO2分離・回収技術を転用した事例で、全国各地に広がる可能性を秘めている。
市は「バイオマス産業都市構想」を掲げて廃棄物を資源として循環する街づくりを進めている。その一環で、CO2分離・回収事業を推進中だ。
事業のきっかけとなったのが、東芝グループのシグマパワー有明が運営するバイオマス発電所「三川発電所」(福岡県大牟田市)。同発電所は、火力発電所などの排出ガスから放出されるCO2を分離・回収する技術の開発拠点としての役割も担い、実証運転を重ねてきた。その実績に注目した市が清掃工場に役立てるアイデアをひらめき、排出ガスの新たな活用策を模索。16年に清掃工場向けCO2分離・回収設備を東芝から導入した。
ただ、火力発電向け技術の清掃工場への応用は一筋縄ではいかなかった。工場の排出ガスに含まれるCO2は濃度の変動が大きい上、金属を腐食させる塩化水素も多く含まれているからだ。東芝ESSは、そうした問題に設備の改良や工夫で対処し実用化。現在、ごみ焼却時に発生する排出ガスの一部から1日で最大10tのCO2を分離・回収している。
この技術は約99.9%という高純度のCO2を取り出せることも特徴だ。低温でCO2を吸収し高温になると放出する化学吸収液「アミン」を排出ガスに接触させてCO2を吸収。その後の工程でアミンを加熱することでCO2を放出させる。今春には、耐久性が高く環境にやさしいCO2吸収液を開発した。
市は回収したCO2を、光合成に必要な有価物としてパイプラインで近隣農家などに供給。野菜や微細藻類の育成に生かすことも狙う。東芝ESSパワーシステム事業部の斎藤聡・炭素利活用技師長は「地域で資源循環も促せるシステムの導入事例を増やし、CO2回収コストの低減につなげたい」と述べた。

