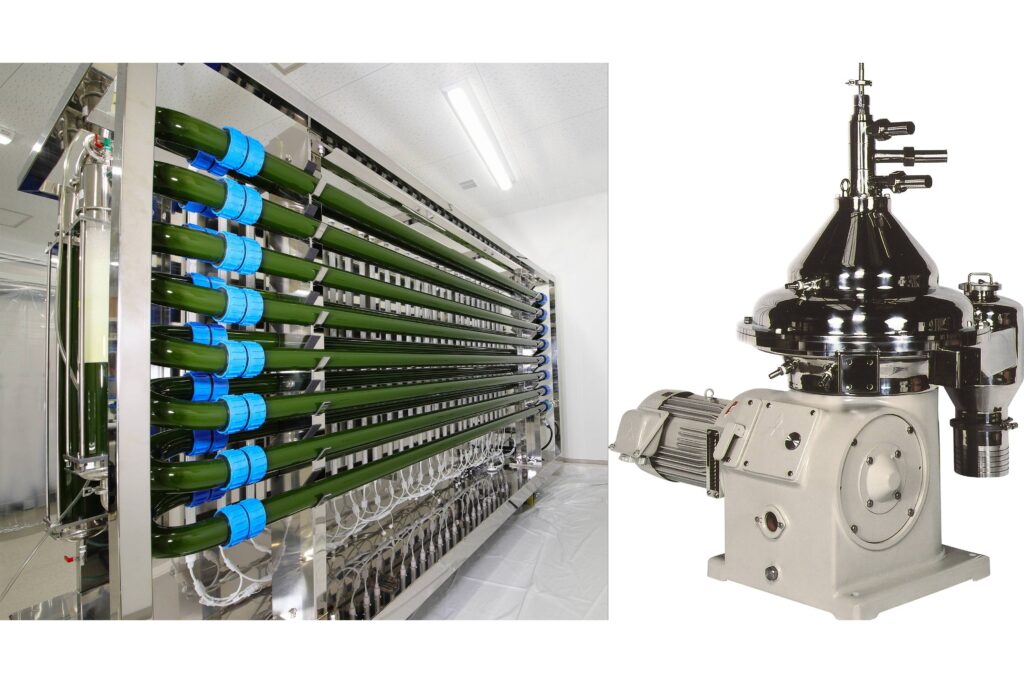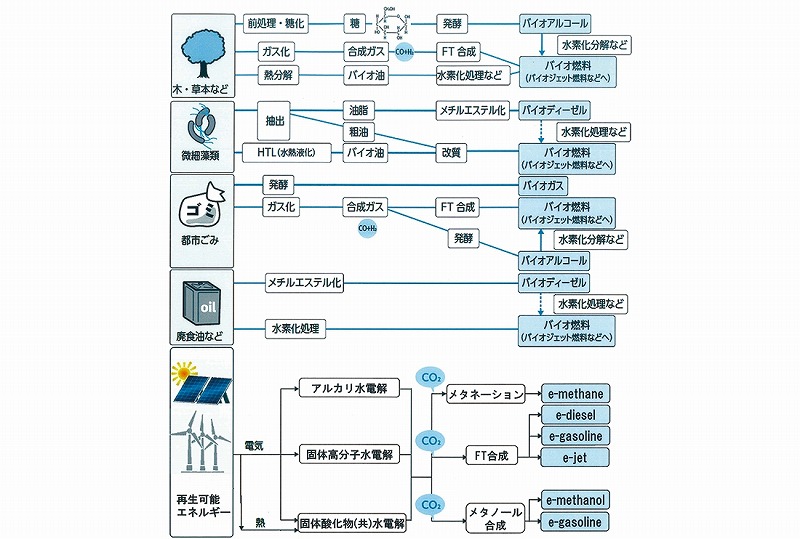【ニチガス】
LPガス輸送のプラットフォームを他社へ貸し出すことで低炭素化を目指す。エネルギーマネジメントシステムの構築によってCO2を大幅に削減する。
都市ガス会社を含めたグループ企業全体で年間263万t程度のCO2を排出しているニチガス。その内訳は、LPガス配送・営業車両の走行などで1.4万t(スコープ1)、自社の電気使用で0.2万t(スコープ2)、エンドユーザーのガス利用で約260万t(スコープ3)だ。
ニチガスでは少量のスコープ2では、非化石証書の活用などによってゼロに近づけているが、その他はどうか。吉田恵一専務は「スコープ1では、当社1社ではわずかだが、当社のLPガス配送方式を他社へ水平展開することで、業界全体でCO2を削減できる」と説明する。
LPガスは、沿岸の元売りの輸入基地から内陸の充てん所を経てエンドユーザーに配送される。一方、ニチガス方式では、輸入基地からいったん「夢の絆・川崎」基地を経由しデポステーション(原則無人管理)を経てエンドユーザーに届く。夢の絆・川崎はLPガス容器を大規模集約し充てんした上で、各地のデポへトレーラーで輸送する同社独自の拠点だ。
容器にはバーコードが印字され、拠点の門を通過する度に、自動でスキャニングされ全容器のデータが集約される。「A地点にX個の容器を運べ」。高度なAIにより、リアルな指令が製造拠点や配送員に知らせる。さらにエンドユーザーの容器内の残ガスを遠隔で日々管理する端末「スペース蛍」とデータ連携することで、最適供給を導く。こうしたDX技術が搭載されたプラットフォームを他社が活用することで業界全体のCO2を削減する。スコープ1でエンドユーザー1件当たり50%のCO2を削減可能だと試算している。
一方、逆パターンもあるという。それはLPガス容器ではなく、あらかじめエンドユーザーにバルクを設置して供給するケースだ。「当社には一部の拠点しかバルク供給の払い出し設備がない。当社も他社拠点を活用し拠点の相乗りで互いの配送を合理化してCO2を削減する」(吉田氏)
蓄電池やヒーポン設備 件当たりCO2を70%削減
本丸のスコープ3はどうか。ニチガスは電気やガスを扱う総合エネルギー企業としてのアプローチを採用する。電気式ヒートポンプとガスボイラーを組み合わせたハイブリッド給湯設備をはじめとして、太陽光発電や蓄電池、電気自動車(EV)などのアイテムを組み合わせてスマートホームを構築する手法だ。
まずは年内に自社の3拠点にパワーエックス社のEV急速充電用蓄電池を導入し、社内からCO2を削減する。次のステップで家庭用蓄電池をエンドユーザーに導入し、太陽光、EVなどと連携して効率的にマネジメントする。現在、エストニアの企業と連携して、これらをスマホで制御するシステムを構築し、新たなサービスとして提供する予定だ。再エネ電気を効率的にヒートポンプや蓄電池、EVに活用しCO2を削減する。
「モデルケースでは1件当たりCO2を70%削減、スコープ3全体では30年にCO2を半減できる」(吉田氏)。エネルギー販売に加えて、エネルギーマネジメントを手掛けることで多くのCO2を削減する青写真を描いている。