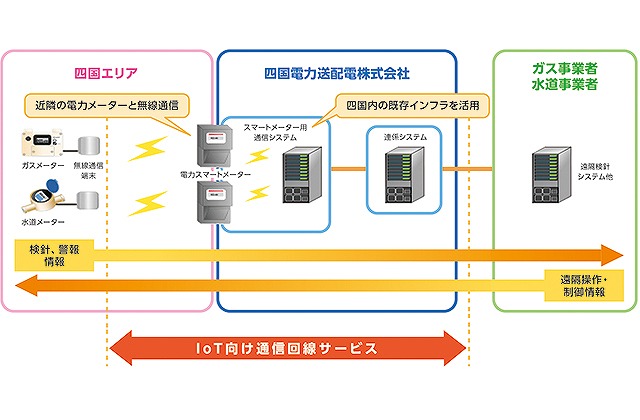【電力中央研究所/窪田ひろみ サステナブルシステム研究本部 気象・流体科学研究部門 上席研究員】

地熱発電事業者向けツールの開発など、電中研では地熱の有効利用に向けた研究を行っている。
これら研究や各種機関の委員も務める窪田ひろみ上席研究員に、地熱発電の現状と展望などを聞いた。
――日本の地熱資源のポテンシャルは世界第3位と言われていますが、地熱開発はなかなか進展していません。その課題は。
窪田 発電を行うには地下から蒸気や熱水を取り出す必要があります。これらの有無や利用可能量は掘削してみないと正確に把握できないため、ポテンシャル試算量の全てが発電に利用できる訳ではありません。また掘削費用は高額であり、有望地の絞り込みには開発リスクが伴うため、民間企業では手を出しにくいのが現状です。
近年、自然公園内での開発に係る規制緩和により開発可能な地域が増えましたが、熱源までの道路、送電線などの整備が新たに必要となり、開発の難易度は未だ高いといえます。さらに地域関係者との丁寧な協議など、時間とコストが掛かります。太陽光や風力などの再生可能エネルギーと異なり、「地上」「地下」「社会」に係るさまざまな配慮が必要です。
――諸課題の解決へ、電中研はどのような研究を行っていますか。
窪田 「社会」の課題を解決するには、開発候補地が抱える地域事情や開発に対する考えを事業者側が理解しなければなりません。また地熱発電の意義やしくみ、開発による便益やリスクなどを地域関係者に分かり易く伝える必要があります。これに関しては、地熱開発に伴う地域産業への経済効果を可視化する手法の調査をNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)事業として進めています。
「地上」「地下」の技術的な面では、例えば石油天然ガス・金属鉱物資源機構と高温岩体発電技術を使って圧力により地中に人工的な亀裂を作り、隙間にCO2を注入して蒸気を作る「カーボンリサイクルCO2地熱発電技術」の共同研究を進めています。他にも配管などを腐食させる硫化水素のIoTモニタリング手法開発など、安全な発電所操業に向けた技術開発もNEDO事業で行っています。
地熱発電の運営を手助け 事業者向けにツールを開発
――「GeoShinkTM(ジオシンク)」と「事業性評価支援ツール」を地熱事業者向けに開発しました。
窪田 FIT導入以降、余剰の温泉や温泉熱を活用した数十から数百kW程度の小規模地熱発電が80件程度増加しました。しかし、設備等のトラブルが多い発電所もあり、全体的に設備利用率は低く、多くの事業者は想定していた程の収益を得られていません。
ひとたび発電設備に故障などのトラブルが起きれば、修理完了までに長期間を要することもあります。発電停止中は売電収益を得られず、FIT対象期間も延長できません。このためNEDO事業で、デジタル技術を使って設備の異常予兆の検知や健全性診断が可能な「ジオシンク」と、定期点検費用、維持管理費用などの支出と、FIT価格などを入力することで、発電事業のキャッシュフローを分かりやすく表示する「事業性評価支援ツール」を共同開発しました。

――両ツールにはどのような特徴がありますか。
窪田 「ジオシンク」は、発電設備の稼働状況のモニタリングデータを解析するツールです。数値の変動を監視することで、故障やトラブルの発生原因を遠隔地から早期に検知することが可能です。
「事業性評価支援ツール」は、電中研とエンジニアリング協会(ENAA)が共同開発したエクセルベースの家計簿のようなツールです。
トラブル要因や対策内容・費用だけでなく、写真形式のデータも登録可能で、紙の領収書や交換部品など、メンテナンスにかかる各種データを一元管理する機能もあります。またジオシンクでの発電電力量の分析結果の一部を計算モデルに搭載しているので、売電収入の近似値を算出できます。事業収支の観点から最適な点検スケジュールといったシミュレーションを事業者自身で行えるので、事業者の最適な設備運用や収益性の向上に繋がることが期待されています。
「地元」「事業者」の橋渡し 持続可能な地熱発電に貢献
――研究の展望を教えてください。
窪田 現在の専門領域は主にリスクコミュニケーションや事業性評価で、事業者と地域関係者の相互理解や信頼醸成に資する事業者側の改善策などを研究しています。例えば、事業者は地熱開発により地域が得られる便益や開発リスクなど、地域の関係者が知りたいあらゆる情報に対応する必要があります。
また地域関係者の信頼を得るためには的確な説明だけではなく、誠意や誠実な対応・態度が重要です。このような学術的・科学的な内容を分かりやすく伝える方法や対話の場づくりなど、双方向的なコミュニケーションを支援しています。
―地熱エネルギー利活用推進に向けて意気込みを。
窪田 地熱発電は現在の電源構成の中で0・2%に過ぎませんが、原子力、水力と同じくベースロード電源としての役割を果たし、更に熱利用により省エネにも貢献しています。
持続可能な地熱資源エネルギー利用により地域内で便益が循環し、地域社会の問題解決にも役立つ環境づくりに貢献したいと考えています。