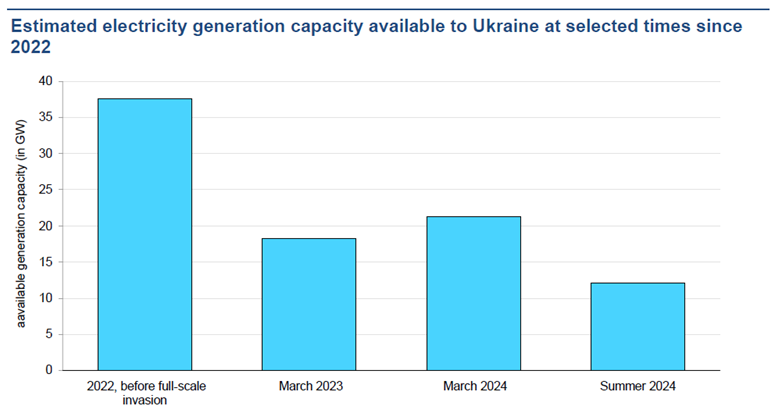テーマ:エネルギー業界から見た概算要求
2025年度予算案の概算要求で一般会計の総額が117兆円超となり、2年連続で過去最大を更新した。エネルギー・環境関係の計上額も大きいが、具体的にはどのような事業が並んでいるのか。エネルギー業界人と内容を総点検した。
〈出席者〉 A石油業界関係者 Bガス業界関係者 C電力業界関係者
―まずは経済産業省の内容から。合計では2・36兆円となり、このうちGX(グリーントランスフォーメーション)・脱炭素エネルギー関連では1・25兆円を計上している。
A 作文は良くできているなとは思うが、今回は新しい玉がほぼ見当たらず、一言で言えば見どころに欠ける。しかも首相交代で下手をすれば予算の内容が変わる可能性もある。これだけ盛り上がらないのも珍しい。
特にGX推進対策費が24年度当初予算より3400億円ほど増えている。エネルギー対策特別会計は前年度並みで、想定の範囲内だ。いずれにせよ額が膨張する傾向は今後も続く中、各項目ではばらまき過ぎだと感じる部分がある。もちろん重要な事業も多くあるが、もう少し整理すべきだろう。概要資料を見てもポイントが今一つ掴めない。
―一昔前は1事業で3桁億円となれば大騒ぎだったが、いつの間にかその程度は当然のように計上されている。
B 確かに目新しさに乏しい。既存事業を膨らませた印象で、特にGX・脱炭素関係でその傾向が顕著といえる。業界からすると、前回の概算要求からGX推進対策費で最大5年間の複数年度の予算感を示し、事業者が投資予見性を見渡せるようになったことはありがたい。

金額だけ膨らむGX事業 メリハリなくばらまき感目立つ
B 今回、概要資料のGX・脱炭素関連の説明の中で「LNG等の安定供給確保」との文言が入っている。審議会などで「長期契約が減っていく中で調達の長期予見性を高めるための支援策が必要だ」といった指摘が出ていることもあり、新しい項目が盛り込まれているのかと思ったが、見当たらなかった。それどころか資源・燃料の安定供給確保に関する事業を拡充しているようには見えない。特に石油天然ガス田の探鉱・資産買収などに対する出資金の事業は、今年度当初予算と比較すると半分の486億円となっていて、気になる点だ。
C 一方、SAF(持続可能な航空燃料)の製造・供給体制構築支援が838億円で今年度当初の約3倍。それで行って来いではないのだろうが、GXに重点ということか。
全体の話に戻し、当初予算でなく概算要求額で前回と今回とを比べると、実は前回24年度の概算要求額が2・46兆円で、今回は減っている。実際の予算編成では財務省に大分削られるから、25年度当初も結局前年度当初並みになると思われる。ただ、当初予算で見ると、23年度1・69兆円から、24年度は1・9兆円と大幅に増えている。
―しかもGX関連では23年度補正に前倒したものも結構ある。
C GXはまさに複数年度継続するという立て付けだから、金額も継続的で良いよねという印象を受けるし、前回増加に失敗した事業では今回も再チャレンジしているんだろう。
A 業界関係者は概算要求に向け、4月末に役所に要求書を出す。例えば石油なら元売りの企画委員会などから新ネタを上げるようにしているが、それにみんな結構悩んでいる。団体側の施策構想力が落ちているから、資源エネルギー庁原課も金額だけ膨張させるという側面もあろう。
特にGX・DX関係は主体が分かりにくい。これはメディアが細かく書かなくなったことの影響もあるのかも。
―加えて、24年度概算要求から資料を経産省全体で統一し、それまでエネ庁が別途1枚紙でまとめていた資源・エネルギー関係のポイントが公表されなくなった。これも分かりにくさにつながっているだろう。
C 特にエネ特関係は第6次エネルギー基本計画に基づき予算を獲得したものを今回もそのまま要求している。今後、総裁選や、年度内に第7次エネ基などが策定される中、この要求がそれらにどう影響されるのか、やはり気になるところだ。
その中で、需要側に関する事業の額が積み増されている点が最近の特徴と言える。政府は、「脱炭素の一丁目一番地は省エネ」が基本姿勢なので、省エネに加えてVPP(仮想発電所)関係などの事業規模の拡大が目立つ。水素でも需要側を含めたサプライチェーン利活用を意識した立て付けだ。また、水素や蓄電池についてはある程度実装が見通せるようになってきたこともあり、力を入れている印象。いずれにせよ、GX・脱炭素に向けては需要側がついてこなければ意味がないので、大胆に補助をするという発想になっている。
―逆に供給側の事業に目玉がないとも言えるのでは?
C 系統用蓄電池などの導入支援(310億円、24年度当初の3・6倍)と、次世代革新炉の研究開発支援(829億円、同1・5倍)が増額されていて、あとは横ばい。原子力をはじめ電力に関する予算を一定確保し、推進に向かおうとしていることは業界的にプラスだと感じている。
A ただ以前から、次世代革新炉開発は1桁足りないのでは、といった有識者などの指摘がある。やはりあらゆる分野に振りまき、金額的にメリハリがついていない予算だ。