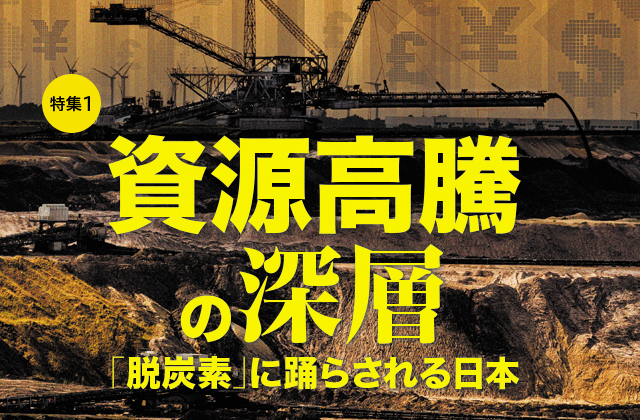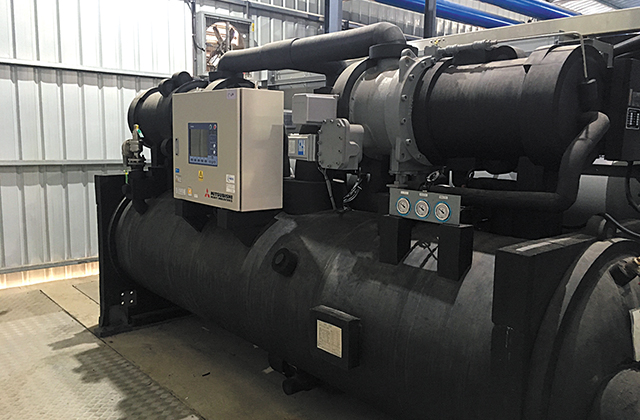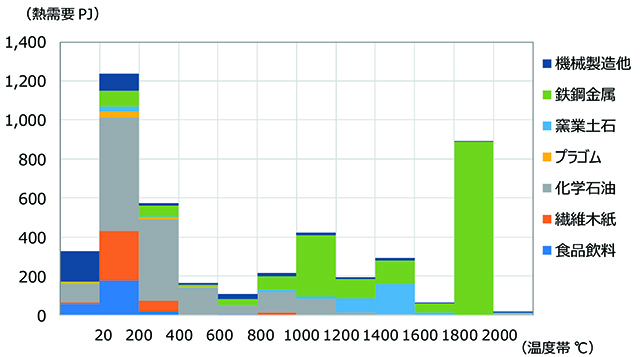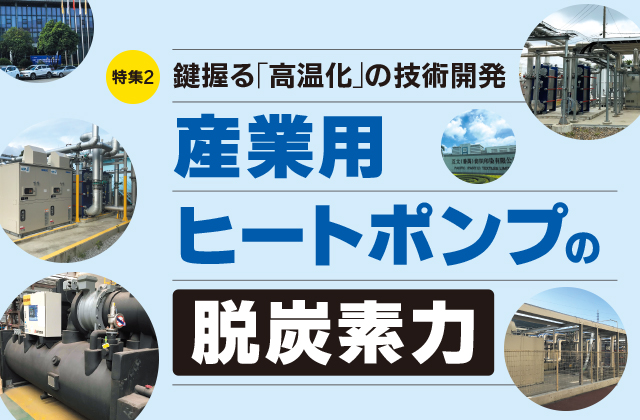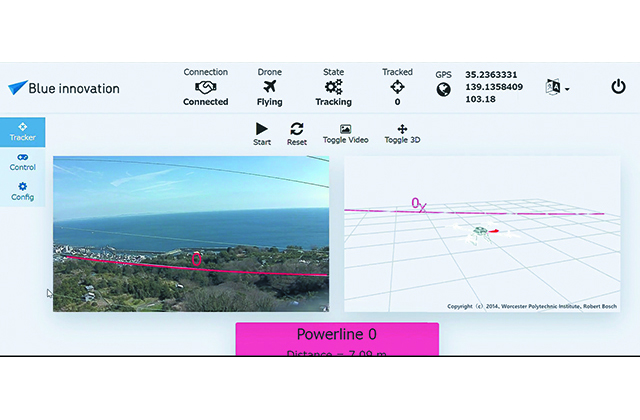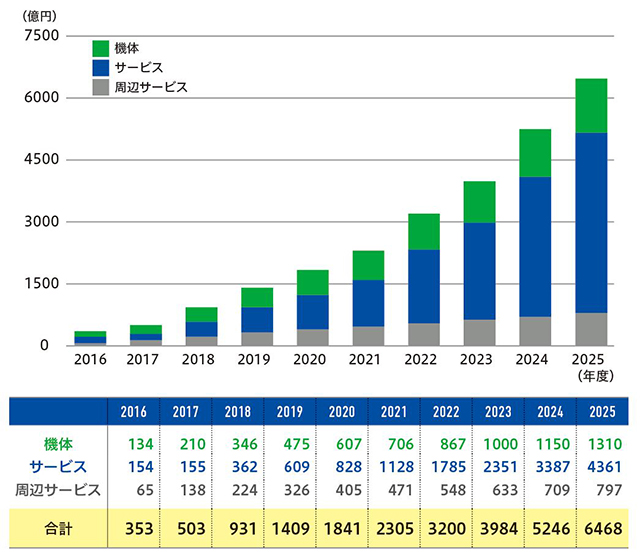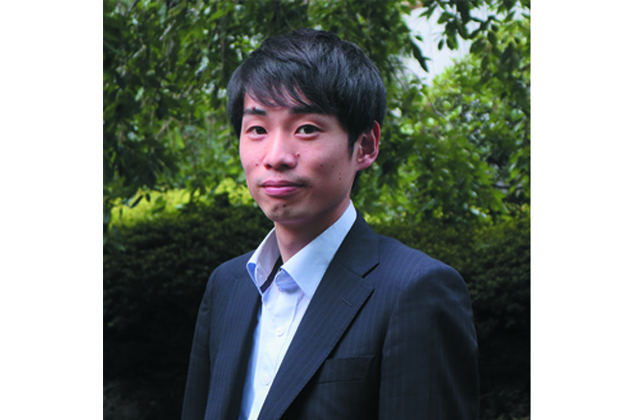【サイサン】
サイサンは事業者と提携して代行サービスを開始した。需要家の生活を支える新サービスで、収益力強化を図る。
サイサンは、需要家の暮らしを支えるサービスとして家事代行・ハウスクリーニングを2020年9月から提供している。
自社と契約している需要家が対象のサービスで、キッチンやバスタブ・空調機器清掃などのハウスクリーニングを行える。清掃業務は同社と提携する家事代行会社「ベアーズ」に登録されている掃除のプロが担当しており、現在は一都三県および愛知県を中心としてサービスを提供している。
新サービスについて、同社経営企画室の松井忠室長は「高齢化社会や共働き世帯の増加で、家事になかなか手が回らない家庭が増えている。ゆとりのある生活を送ってもらいたいとの思いから、新サービスを計画した」と説明する。
海外では家事代行やハウスクリーニング、ベビーシッターなど代行サービスは一般的に利用されている。しかし日本では自宅に他人を招き入れて掃除をしてもらうことへの抵抗感が根強いことから、家事代行業界も、自社サービスの普及に頭を悩ませているという。
その点で、業務部営業企画課の神田啓介課長は「LPガスや電気の契約でお客さまとの接点も多く、当社に対する信頼感もあるので、こうしたサービスを広めやすい」と語るなど、LPガス事業者は日頃から多くの需要家と接点があるため、アドバンテージがあるという。
実際、21年6月には夏場のエアコン需要に合わせて清掃サービスを期間限定で実施したところ、数百件の申し込みがあった。この数字はベアーズと代理店契約を結ぶ各種事業者が受注した件数のうち、約3割を占めるそうだ。
10月からは年末の大掃除シーズンに向けたキャンペーンを予定している。またスポットではなく定期的に需要家宅を訪れる家事代行サービスもラインアップしており、今後は認知度向上に向けた各種施策を行いながら、定期サービスの契約者数を増やしていきたい考えだ。
生活のトラブルを解決 駆けつけサービスも提供
ホームクリーニングに加え、同社は需要家の生活を支えるサービスとして「サイサン駆けつけサービス」も提供している。
これは洗面台やトイレなど水回りの故障やガラスの破損、鍵の紛失など生活トラブルが発生した際に、24時間応対の専用の窓口に連絡することで修理業者が駆けつけて対象物を修理する月額課金型のサービス。
ほかにもさまざまなテーマパークやホテル、スポーツジムなどの料金が割引となる会員優待サービスも提供しており、クリーニングサービスと駆けつけサービスがセットになった料金プランも用意している。
暮らしに役立つ各種サービスで需要家の満足度を高めながら、収益力強化を図っていく方針だ。