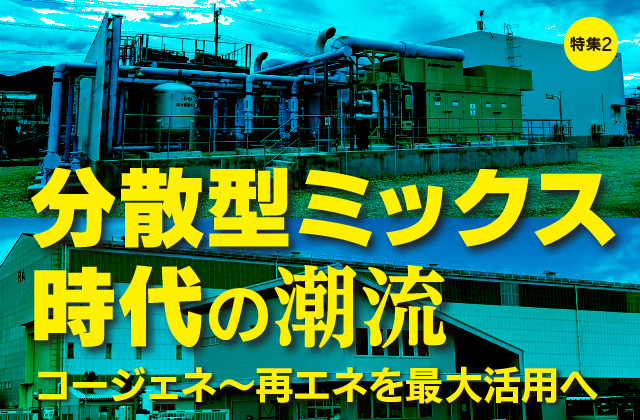地域資源を生かす多様なベースロード再エネが津々浦々に広がっている。
一段の導入拡大に向けて開発コスト低減など数々の壁も立ちはだかる。
天候などの自然条件に左右されにくく安定的に発電できる―。そんな「ベースロード(基幹)電源」の役割を担える多様な再生可能エネルギーへの期待感が、全国各地で高まっている。脱炭素化にとどまらず、発電設備の建設や運用などを通じて導入地域に経済効果をもたらす可能性を秘めているからだ。一方で導入拡大に向けた課題も抱えており、関係者には持続可能な事業モデルづくりで創意工夫する力量が試されている。
30年度導入目標が目前に バイオマスが存在感を発揮
ベースロード再エネの一つが、森林由来の間伐材をはじめとする生物由来の未利用資源を燃焼する際の熱を用いて電気を起こす「バイオマス発電」。発電した後の排熱は、周辺地域の暖房や給湯向けに役立てられる。
資源エネルギー庁によると、バイオマス発電は2012年に固定価格買い取り制度(FIT)が開始されて以降、着々と導入量が拡大し、3月末に約7・5GWに(1GW=100万kW)到達。30年度の導入⽬標8・0GWに近い水準を実現した。
中でも未利用木材を燃やしてタービンを回し発電する「木質バイオマス発電」に目を向けると、国産材を燃料に生かす機運が高まっている。国土の約3分の2が森林に覆われた日本の林業を振興するなど、雇用を含め地域を活性化する効果が見込めるからだ。
これまで外国産の木材を利用した発電施設が増えてきたが、風向きが変わりつつある。背景には、世界最大の木質ペレット製造業者で知られる米エンビバが3月に破産を宣言した動きがあり、輸入材の安定調達が揺らぎ始めている。政府も国産材の活用促進に意欲を示しており、国産材へのシフトが進む可能性がありそうだ。
 木質バイオマス発電向け未利用木材 提供:三洋貿易
木質バイオマス発電向け未利用木材 提供:三洋貿易
バイオマス発電の導入促進に向けては、コストの大半を占める燃料費の低減が鍵を握る。さらに燃料需給がひっ迫する傾向にもある中で政府は、燃料安定調達の観点から成長の早い早生樹などを生かす実証事業を後押しする。
一方、河川や農業用水、上下水道などに流れる水のエネルギーで水車を回して発電する「中小水力発電」も各地で存在感を発揮。導入量はバイオマスと同様、直近で30年度の目標10・4GWに迫る10・0GWに達した。
ただ、有望な開発地点から優先的に開発した結果、適地が減少。残された開発可能地点の多くは奥地にあり、開発が長期にわたりコストがかさむという課題に直面している。このため、開発時のコストとリスクの双方を低減しながら地域と共生できる導入スキームを実現する対応が求められている。
地中深くから取り出した蒸気でタービンを回し発電する地熱発電もベースロード再エネの一翼を担う電源で、エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)の支援制度を活用した事例が積み上がっている。3月には、JOGMECの開発資金債務保証を活用し、三菱マテリアルと三菱ガス化学、電源開発(Jパワー)が共同出資する「安比地熱」(岩手県八幡平市)の発電所が営業運転を開始。JOGMECは先導的な資源量調査も行っており、20~23年度に全国で延べ約80件を実施したという。
 運転を始めた安比地熱発電所 提供:安比地熱
運転を始めた安比地熱発電所 提供:安比地熱
とはいえ足元の導⼊状況を見ると、0・6GWにとどまっているのが現状。地元調整などを含む事業開発に長期間を要すると想定される中、30年度⽬標1・5GWとの間に大きな開きがある。目標達成に向けて政府は水力発電と同様、リスクとコスト面を考慮した地域共生型の導入を促そうとしている。
イノベーションにも熱視線 地熱発電技術が進化へ
地熱発電を巡るイノベーション(技術革新)の行方にも熱い視線が注がれている。政府は、世界有数の地熱資源量を誇る日本で「開発可能な資源量」を増やそうと次世代の地熱発電技術の開発に取り組む方針を、現行の第6次エネルギー基本計画に盛り込んだ。
この中で「高温岩体地熱発電」や「超臨界地熱発電」といった次世代技術にも触れ、「世界に先駆けて技術開発から社会実装、そして世界展開へとつなげていくことで、50年のカーボンニュートラルに貢献していく」と明示した。超臨界地熱発電は、マグマに近い深部にある400〜600℃の熱水を生かして発電する仕組みだ。
地熱発電を利用する可能性を広げる動きは世界規模で活発化し、消費電力が多いデータセンター(DC)の需要増加に対応する切り札としても注目される。米グーグルはスタートアップと組み、ネバダ州のDCにつながる地域送電網へ電力の供給を始めた。「脱炭素化と安定供給の観点から多様なオプションをバランスよく見極めたい」とエネ庁新エネルギー課。日本の電源構成で10%超を占めるベースロード再エネの最前線に迫った。