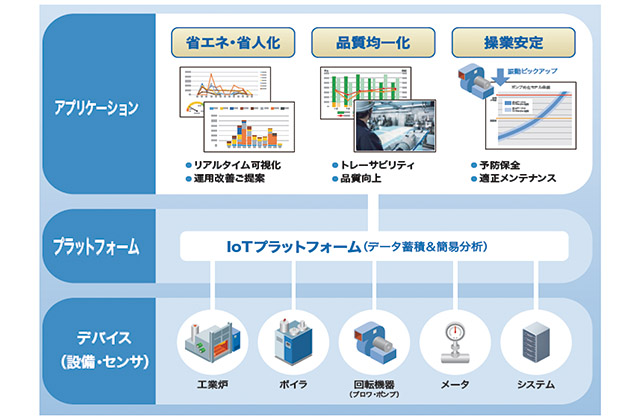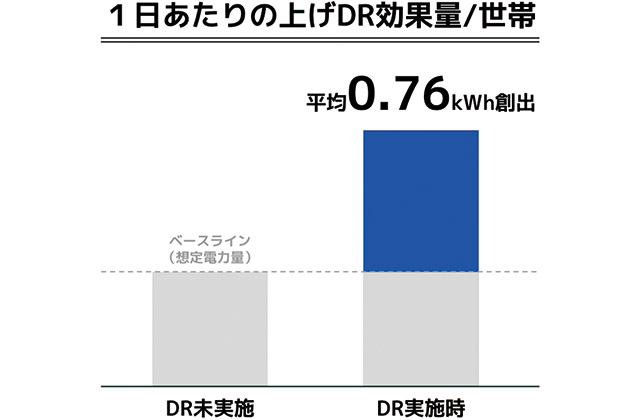【中国電力・東洋鋼鈑/中国地方初の営農型PVでオフサイトPPA開始】
中国電力は山口県内の営農型太陽光発電(PV)を活用した電力供給契約(オフサイトPPA)を東洋鋼鈑と結び、電力供給を始めた。中国地方では初となる営農型PVで、中国電力としても初の取り組みだ。これまでエコスタイル社、彩の榊社と3社で協業を進め、農地の上部空間に太陽光発電設備を設置するスキームを検討してきた。営農型は、農作物の栽培によるCO2削減や再エネ導入量の拡大につながる。耕作放棄地の再生利用や農業経営の改善による農業の活性化にも期待が持たれている。今回の営農型PVでは、太陽光パネルを隙間なく並べ、遮光率が50%程度であることから、陰性植物である「榊」を栽培する。また東洋鋼鈑向けに計6万4000kW分の営農型PVを開発する。
【サミットエナジー・NEC/サミット電源活用し需給調整市場に参入】
サミットエナジーとNECは、電力の需給調整市場に参入した。サミットエナジーが保有するサミット美浜パワーの電源である1万7000kW級のガスタービン(2基)、1万5000kW級の蒸気タービン(1基)を活用し、最大7500kWを市場に出す。サミットエナジーが発電リソースを提供するほか、入札戦略や運転計画を立案する。一方、NECはリソースアグリデーターとしての役割を担う。アグリゲーションコーディネーターである東京電力ホールディングスからの制御指令に基づき、発電リソースに対して制御指令を伝達する。出力が変動する再エネの普及が進んでおり、需給調整の機能が重要になっている。市場を介した調整力機能の供出により、再エネの大量導入時代に備えていく。
【ユーラスエナジー/道北風力発電事業4カ所目が稚内で運開】
ユーラスエナジーホールディングスのグループ会社の合同会社道北風力が、北海道稚内市で建設を進めていた「樺岡ウインドファーム(4万2000kW)」が完成し、2月から営業運転を開始した。同発電所は、道北地域に全6カ所の風力発電所、計107基の風力発電機を設置する「道北風力発電事業」の一環で、「浜里ウインドファーム」「川南ウインドファーム」「川西ウインドファーム」に続く4カ所目の発電所だ。1基当たりの出力が4200kWのGEベルノバ社製の風力発電機を10基設置し、発電する電力は北海道電力ネットワークへ全量売電する。一般家庭約3万1000世帯の消費電力に相当する電力を供給するとともに、年間4万7000tのCO2削減効果を見込む。
【関西電力/CO2回収試験ラインを関電姫路第二に建設】
三菱重工業は、関西電力と共同で関電姫路第二発電所にCO2回収パイロットプラントを設置する。次世代CO2回収技術を検証する試験設備を設けるもので、2025年度の稼働開始を目指す。同設備では、発電所にあるガスタービンからの排ガスを用いてCO2回収技術の研究開発を行う計画。22年にエクソンモービルと合意した提携に基づき共同開発中の次世代CO2回収技術を実証し、環境負荷低減とコスト削減に向けた研究開発を加速し、競争力強化を図っていく。
【日本原子力産業協会/エネミックスを学ぶ ボードゲーム発売】
日本原子力産業協会は1月、東北大学の協力を得て「エレクトロネーション―エネルギーミックスボードゲーム―」を発売した。ゲーム原案・監修は遊佐訓孝東北大学教授、ボードゲームデザイナーはカナイセイジ氏。このゲームの目的は、幅広い世代にエネルギーミックスが国の発展・繁栄を左右し得るかを理解してもらうことだ。各プレイヤーは国家のエネルギー管理者として、自らの国が必要としている電力供給量を確保し、温室効果ガス排出量の制限を守りながら国を発展させていく。本体価格は税込み4950円。
【大林組/水素を鉄道で輸送 脱炭素化を実現】
大林組は1月、大分県玖珠郡で製造されたグリーン水素を鉄道で輸送した。従来のトラック輸送に比べ、輸送時のCO2排出量を82%削減した。水素の鉄道輸送の取り組みは国内初。同社はCO2排出量削減に資する各施策の実証の一つとして、岩谷産業の建設現場(兵庫県神戸市)に水素燃料電池を設置している。その電力供給用として玖珠郡から神戸市までグリーン水素をトラック輸送していたが、長距離輸送時のCO2排出量削減のため鉄道輸送に切り替え、1回の輸送のCO2排出量を0.347tから0.062tに削減した。
【双日・イオンモール/インドネシアのイオンで屋根置き太陽光発電の稼働開始】
双日とイオンモールは、双日の持分法適用会社であるピーティー・スルヤ・ニッポン・メサンタラ(SNN)社を通じて、インドネシアの1号店「イオンモールBSD CITY」に屋根置き太陽光発電設備を導入、2024年1月に稼働を開始した。BSD CITYの屋上に総面積約4,244㎡の太陽光発電パネルを設置し、年間の発電量は合計116万1000kW時を計画している。年間のCO2排出量を約712t削減する見込みだ。さらに、同国で建設中の5号店「イオンモール デルタマス」においても屋根置き太陽光設備の設置を進めている。双日は、蓄電池、EV関連事業、省エネ、水素・アンモニア・バイオ燃料などのゼロエミッション燃料供給サービスなども提供する予定だ。
【東京ガス/米国最大級となる太陽光発電所が完工】
東京ガスの100%出資子会社である東京ガスアメリカ社は、米国テキサス州における「アクティナ太陽光発電事業」の発電所の建設工事を完了した。本事業は、建設工事の全工程を4期に分け、2021年8月から順次部分稼働を進めており、23年12月に全稼働した。本事業の最大出力は63万kWで、米国最大級の太陽光発電所となる。また今後、米国では系統用蓄電池事業への参画も予定しており、海外事業の利益目標500億円に向けて収益基盤を強化していく。
【関電工/技術開発報告会を開催 800人近くが参加】
関電工は「2023年度技術開発報告会」を都内で開催した。赤司泰義・東京大学大学院教授による「カーボンニュートラル時代の建築設備」をテーマにした基調講演のほか、「地中送電土木技術に関するCO2削減の取り組み」「設備データ分析による施設運用の効率化」など、関電工独自の技術の発表が行われた。オンラインを含め800人近くが視聴参加した。
【東急不動産・ENEOS/SAF原料に廃食油活用 和歌山製油所で製造】
東急不動産とENEOSは2月7日、SAF(持続可能な航空燃料)の製造で連携すると発表した。東急不動産グループが全国で運営するリゾート施設29カ所などから廃棄される食用油を回収し、ENEOS和歌山製造所でSAF用製造プラント(年間40万kl)の原料として使用する予定だ。国際的に化石燃料からの脱却を進める航空業界向けに活用する。
【積水ハウス/日産自動車/EV導入の障壁減らす 普及プロジェクトが発足】
日産自動車と積水ハウスはこのほど、ゼロエミッション社会と快適でエシカルな暮らしの実現に向け、EVをより身近に選択できるための「+e PROJECT(プラスイープロジェクト)」を発足した。EV購入検討層が増加傾向にある中、集合住宅にEVの充電設備がないことが購入の障壁であるという日産の調査結果を踏まえ、住環境とEVのより良い関係性を目指す多様な施策を展開していく。1月には、「EV充電設備と集合住宅の未来価値」をテーマにしたSFコメディWEBドラマ『未来にまかせる君』を公開した。