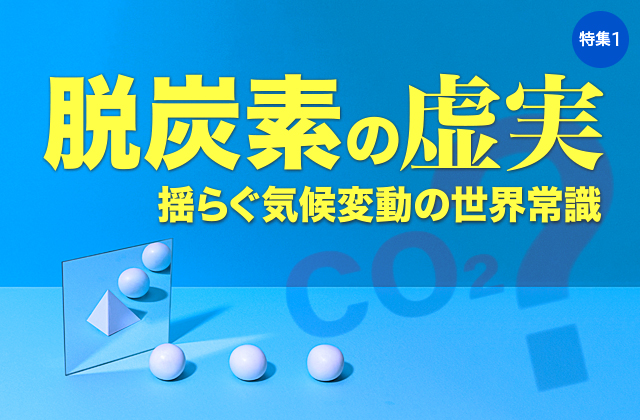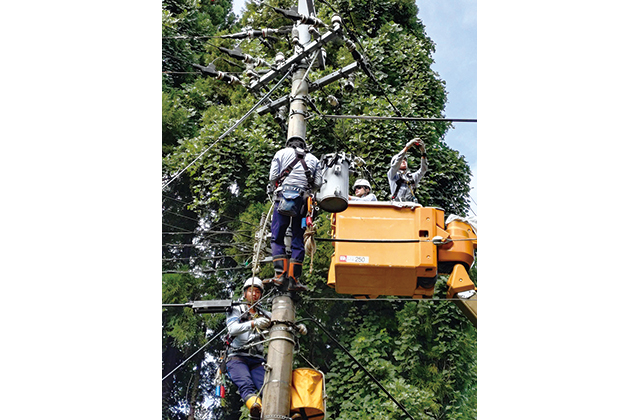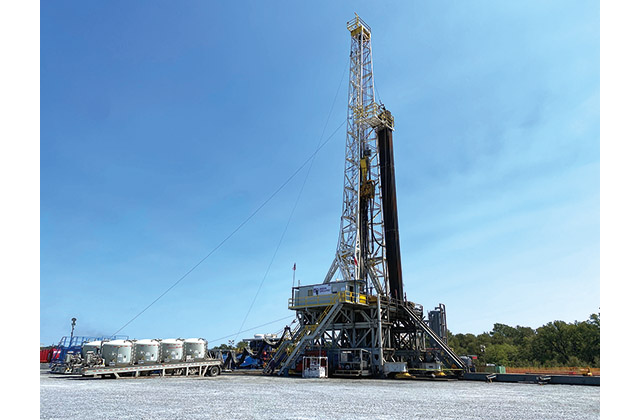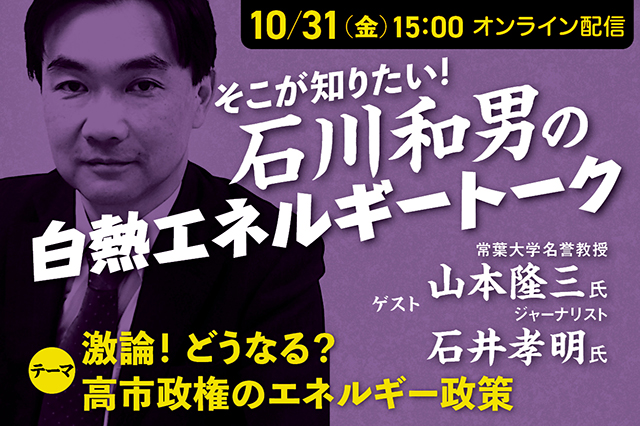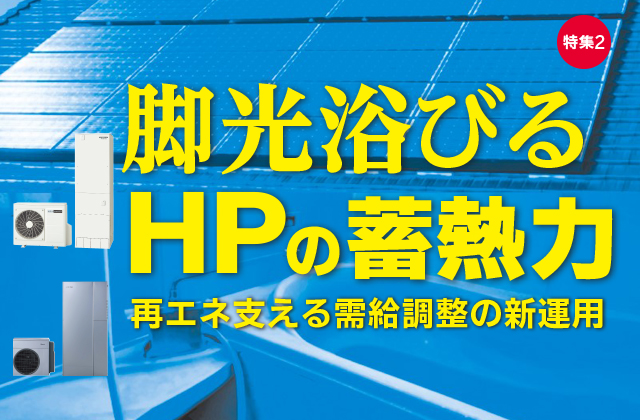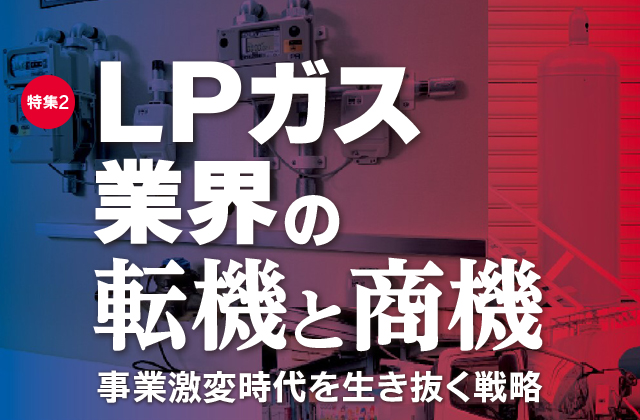女川2号機は安定運転を継続し、「財務基盤の早期回復」にも道筋が見えてきた。
想定以上に厳しい事業環境の中、AI、データセンターといったビジネスチャンスを的確に捉え、自社の強みをこれまで以上に生かした事業展開を考え抜く。
【インタビュー:石山一弘/東北電力社長】

門倉 社長就任から9カ月、これまでを振り返って手ごたえや課題感などいかがでしょうか。
石山 就任以降、「実行力とスピード」重視の経営に全力で取り組んできました。改めて振り返ると、あっという間の9カ月だったと感じます。
当面の優先課題として注力してきた財務基盤の早期回復については、着実に進捗してきています。また、2024年12月に、14年ぶりに営業運転を再開した女川原子力発電所2号機が、大きなトラブルなく安定運転を継続できたことは、電力の安定供給やカーボンニュートラルへの貢献の観点から、大きな意義があると考えています。社員や協力企業はもとより、日ごろから当社の事業運営を支えていただいている地域の皆さまのご理解のおかげであり、心より感謝を申し上げます。1月14日からは、再稼働後初となる定期事業者検査を予定していることから、しっかりと対応していきます。
一方、東通原子力発電所で発生した核物質防護を巡る不適切な取り扱いについては、原子力事業への信頼を損なうものであり、極めて重く受け止めています。再発防止を徹底し、二度とこのようなことが発生しないよう真剣に取り組んでまいります。
当社を取り巻く事業環境については、電力小売り競争の激化、物価・金利の上昇と円安、米国政策に起因する国内経済の不透明感の高まりなど、想定以上に厳しくなっています。25年度は、一定程度の利益が確保できる見込みではありますが、足元ではフリーキャッシュフローが厳しい状況であることに加え、今後、電力の安定供給をはじめカーボンニュートラルへの対応やDXなどの成長への投資が控えていることを踏まえると、中長期的に稼ぐ道筋をつけることが重要だと考えています。
女川3号機・東通1号機 再稼働に向け着実に対応

門倉 女川2号機の再稼働から1年以上が経過し、女川3号機・東通1号機の再稼働も期待されます。それぞれの現状を教えてください。
石山 女川3号機も東通1号機も重要な電源であり、各プラントの状況に応じて、対応すべきことを一つひとつ着実に進めていきたいと考えています。
女川3号機については、新規制基準適合性審査申請に向けた準備の一環として、25年1月20日から地質調査を実施しています。また、地質調査以外にも、女川2号機の審査で得られた知見・評価などを踏まえ、安全対策設備の配置計画検討などを実施する必要があります。現時点で申請時期を具体的に申し上げる状況にはありませんが、しっかりと準備を進めていきます。
東通1号機については、将来にわたって長期に、かつ安全に運転していく観点から、基準津波に対する裕度を高めるため「敷地造成」を計画し、現在その審査に対応しています。また、並行してPRA(確率論的リスク評価)津波対策の検討や安全対策設備の配置検討などのプラント審査準備を進めており、安全対策工事の完了時期の公表については、27年3月頃を目指しています。今回の不適切事案についてはしっかりと反省し、この教訓を生かすことで、再発防止を徹底します。その上で、地域の皆さまからのご理解をいただきながら、できる限り早期の再稼働を目指していきます。