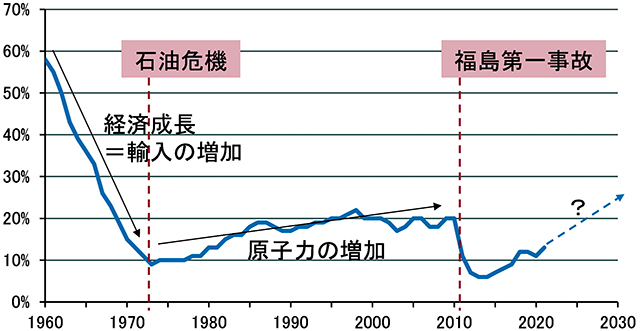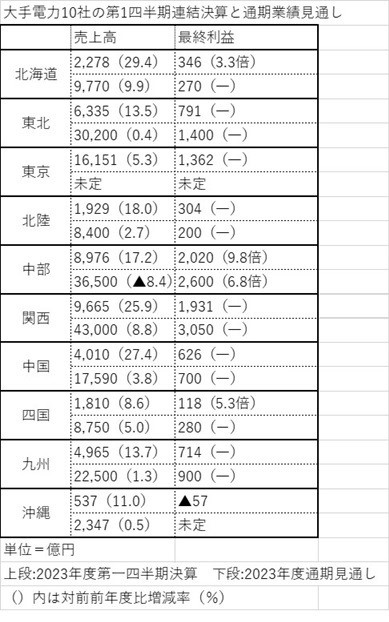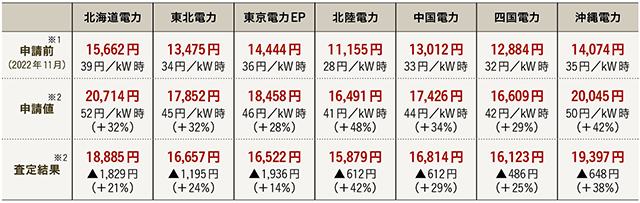脱炭素化へのトランジション、そして地域の課題解決に向け都市ガス事業者による貢献への期待は大きい。業界のビジョン推進と各事業者の対応をどう支援していくのか。日本ガス協会の本荘武宏会長に聞いた。
【インタビュー】本荘武宏/日本ガス協会会長

―2050年カーボンニュートラル(CN)への第一関門として、30年温暖化ガス46%削減というNDC(国別目標)の着実な達成が求められています。
本荘 わが国の産業・民生部門のエネルギー消費量の約6割を占める熱需要の低・脱炭素化はCN化の鍵であり、ガス体エネルギーが果たす役割は大きいと考えます。都市ガス業界としては、21年6月に発表した「カーボンニュートラルチャレンジ2050アクションプラン」に基づき、取り組みを着実に進めています。
―その進捗について手応えはどうでしょうか。
本荘 トランジション期では、NDC達成への即効性がある、①ほかの化石燃料からの天然ガスシフト、②分散型のコージェネレーションや燃料電池などの普及拡大によるガスの高度利用、③クレジットでのオフセットを活用した「カーボンニュートラルLNG」の導入拡大―などを強力に推進していきます。大手と地域の事業者が手を携え、その波は着実に広がっています。
そして将来的には、都市ガスを脱炭素化した「e―メタン」へと置き換え、既存のインフラを有効活用しながら、シームレスにCN化を実現させたい考えです。
なお、25年開催予定の大阪・関西万博ではガスパビリオンを出展し、都市ガス業界の取り組みを発信していきます。まさに「未来の実験場」として、CN化やCO2リサイクルを来場者の皆さまに実感してもらえるような空間を提供します。ガス業界が今後も人や地域、社会に寄り添う存在であり、将来への期待も感じてもらいたいと思っています。
―他方、政府はGX(グリーントランスフォーメーション)に巨額予算を投じ支援を拡充するとともに、カーボンプライシング(CP)の一環で化石燃料賦課金などの導入も予定しています。
本荘 政府に対しては、業界を挙げてGXにおけるe―メタンの重要性をアピールしており、社会実装に向けては、水素・アンモニアで検討されているような支援の具体化にも期待しています。加えて、都市ガスへの燃料転換、エネファームやエコジョーズなど省エネ機器普及へさらに支援をいただけるとありがたい。
そしてCPについては、将来の成長を妨げないような制度設計となること、賦課金が適切な手法でe―メタンなど日本の脱炭素化に資する支援となるように期待しています。